start-editing_20260120,20260203,20260217,20260303,20260317,20260331_end


Interviewee
蛭子 彩華
MARKETING HORIZON 編集委員
一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事
クリエイティブデザイナー
Interviewer
福島 常浩
MARKETING HORIZON 編集委員
株式会社AEOS 取締役
「社会課題×デザイン」をテーマにご活躍され、実際にもバングラデシュと日本を結ぶ「わらじプロジェクト」に関わり続けてこられた蛭子彩華さん。とてもエネルギッシュかつ優しい目線で身近な社会課題解決にも取り組まれている蛭子さんに、デザインへの想いやよりよい社会を築いていくための方策などをうかがいました。
福島 まず、編集委員になられたきっかけを教えていただけますか。
蛭子 2019年に編集委員の見山謙一郎先生にお声がけいただいたのがきっかけで、ホライズンには6年ほど携わってきました。その頃は第2子に恵まれて、待機児童を抱えながらの仕事で時間に追われていましたし、私は国語がまるで駄目で、マーケティングのこともわからないですからと編集委員になることを固辞したのですが、先生が笑顔で「大丈夫!」と背中を押してくださったので結局お受けすることになりました。
実は私は、大学時代の2011年に見山先生の授業を取っていて、大学4年生からの長いご縁になります。専攻は社会学だったのですが、たまたま受講した見山先生の経営学の授業で「BOP:Base of the Economic Pyramid:低所得者層)ビジネス」の講義をされていたのがとても衝撃的でした。実際に当時アジア最貧国と呼ばれていたバングラデシュをフィールドにして学生主体のプロジェクトをやろうと声をかけてくださり、先生や仲間とともに「わらじプロジェクト」を始めました。
大学卒業後は一度IT企業に就職し、その後結婚して夫の仕事で南米のチリ駐在に帯同していたのですが、第1子を妊娠して出産のために帰国したタイミングで見山先生にお会いしたのです。そのとき、プロジェクトを運営している現役の学生たちが皆卒業を控えていて人手不足になっている一方で、バングラデシュでは着実に職人を育成し始めて雇用も生まれてきていた状況で、それならば「法人をつくったほうがいいのでは」とお伝えしたところ、その流れで「彩華が代表だね」ということになりました。それが2016年です。法人と第一子のダブル出産をした年でした。
福島 そうですか。蛭子さんはてっきりデザイナーさんだと思っていました。マーケティングのご専門でデザインもできるすごい方だと。
蛭子 いえいえ、とんでもないです。私は、IT企業のサラリーマンをやりながら、週末の時間のあるときに独学でAdobe Illustratorを学びながら友人から頼まれた名刺デザインをしたりもしていましたが、一貫して私のテーマは、「社会課題×デザイン」です。「わらじプロジェクト」もその想いで取り組んでいます。布製のわらじをバングラデシュでフェアトレードの仕組みで生産し、日本で販売することで現地での雇用創出を目指しています。
福島 BOPビジネスとの出会いについてもう少し教えていただけますか。
蛭子 先ほどもお話ししたように、BOPビジネスとの出会いは見山先生の授業でした。同じく先生の授業を受講していた仲間とともに大学4年生の夏休みにバングラデシュへフィールドワークに行きました。そこでとても衝撃的というかカルチャーショックをたくさん受けました。仲間とも話していたのですが、「貧困」や「幸せ」って何だろうということを深く考えるようになりましたね。
経済的に日本は先進国ということで自分を含めた学生たちが上から目線だった点は反省しなければならないのですが、スラム街を訪れたとき、何より感じたのは皆さんとてもエネルギッシュで、ずっと笑顔で分け隔てなく話しかけてくれてとてもフレンドリーでした。逆に現地の大学生と交流した際には「日本は裕福でとても豊かな国なのに、なぜ自殺をしてしまう人が多いのか」と質問されたことも衝撃的でした。そのときに、日本は豊かさと引き換えに失ってしまったものがあるのではないか。精神的に貧しくなってしまったのではないかという疑問が生まれました。
そこからBOPビジネスは現地のためにもなるけれど、日本の私たちが自分自身を見つめ直すためにもなる。お互いに学び合い、継続的に両国がボトムアップしていくことができるのではないかと強く感じるようになりました。今でもこのプロジェクトを進行しながら学び、そして問い続けているところです。
福島 「わらじプロジェクト」とは具体的にどのような事業なのですか。
蛭子 このプロジェクトは、見山先生がドイツで開催された国際フォーラムで見聞きした「1ユーロシューズプロジェクト」というアディダスがバングラデシュで展開していた先行事例があります。バングラデシュの人々は1日約2ドル以下で生活しているがゆえにほとんど靴を履いておらず、足から病気になって最悪の場合亡くなってしまう社会課題がありました。この現状に対して、アディダスがシューズメーカーとして何ができるかとなったときに、1ユーロで靴を売って、多くの人に履いてもらうことを目指した取り組みでした。しかし、工業製品である靴を1ユーロで製造して売るモデルはビジネスとして持続可能ではありませんでした。
見山先生は、このアディダスが果敢にチャレンジしている姿勢に感銘を受け、日本に戻った際にゼミ内で話題にしてくださいました。そうすると一人の女子学生が、「バングラデシュと日本とはお米を食べているという共通の食文化があるので、現地に稲があるはず。日本の伝統的なわらじの技術を教え、米を食べた後の余った藁を使ってわらじをつくれるようになれば、自分たちでも足を守れるし、プロダクトができれば日本へ輸出もできる。新たな雇用創出につながるのではないか」というアイデアを出したのです。そのような学生の柔軟な発想でプロジェクトが始まったわけです。
このアイデアに共感した20人ほどのメンバーで、じゃあ実際に現地に行こうとなったのですが誰もわらじなど編めないということで、秋田県にいらっしゃるわらじ職人に編み方を教わりに行って技術を習得しました。そして実際に、プロジェクトを本格的に始動させるためにバングラデシュへ渡航し、世界最大のNGOであるBRACに運営パートナーになってもらうためにプレゼンテーションも行いました。


ところが想像もしなかったことですが、実は藁は、家畜の飼料や堆肥に使われる貴重な資源でわらじには使いたくないと言われてしまったのです。実際には藁は余っていたのですが、現地の方にしてみればインサイト的に使いたくないということだったのでしょう。仮説は総崩れです。
「プロジェクトはここで終わってしまうのだろうか?」と皆に不安がよぎりましたが先の話がありました。彼らから「バングラデシュは縫製大国でTシャツにならなかった綺麗な余りの生地がある。今までは燃やしてしまっていたが、これを裂けば布でわらじをつくれるのではないか」と逆提案をしてくれたのです。その想像もしていなかったアイデアから商品改良をして布わらじをつくり、ルームシューズとして日本で販売し始めるようになったという経緯です。


バングラデシュの職人がつくった布わらじ。ルームシューズブランド『ami tumi(アミ トゥミ)』として日本で販売し、その利益を現地に還元するという循環型のビジネスモデルで運用されている
福島 蛭子さんは、天性のものかもしれませんがアドレナリンがたくさん出てくる力を持っているように感じます。それに行動力も素晴らしい。
蛭子 そう言っていただきありがとうございます。自分が好きなことには時間も忘れて熱中してしまい、気づいたらやっているような性格なのだと思います。私は美大に憧れがありましたし、親や先生も私が美大に進学するのだろうと思っていたそうなのですが、実は幼少期から社会学的なことの方により興味がありました。何でこうなっているのだろうと考えたり調べたり、その結果視野が開けたりという感覚が好きで、社会学部に進みました。それで見山先生や同じ思いを持つ仲間にも出会えて今があるということを考えると、自分の中に芽生えたワクワクした気持ちを大切にして、自分の心がより惹かれる方向に進むのが心地よいと感じています。そういう気持ちはこれからも大切にしていきたいと思います。
福島 蛭子さんは、“好きになる力”が強い方だと感じました。ある本に書いてあったのですが、目の前にある仕事を一生懸命やってみることから好きになるんだと。一生懸命やると仕事は楽しくなる、好きになる。この仕事は嫌い、自分とは合わないなどと思っている人は自分の人生を狭めてしまっているように思いますね。そういう意味で、蛭子さんは“好きになる力”がすごいのだと思います。
福島 話を進めますが、蛭子さんにとってマーケティングとは何でしょう。
蛭子 私はマーケティング専門で学業や仕事をやってきたわけではないのですが、ホライズンの編集委員に携わってきて感じることは、「マーケティングは愛」ということです。自分が何かをつくりたい、自分が人に何かを伝えたいという想いの根っこには目には見えない愛情があり、それが人の心を動かしているのだろうと感じます。私もホライズンの仕事でたくさんの方々にインタビューをしてきましたが、皆さん本当に温かくて、愛情を持って社員の方やお客さま、あるいはものづくりに向き合われているのを肌身で感じました。それは一言で言うなら「愛」なんだろうと思います。
福島 マーケティングとは「愛」、本当にそうですね。相手のことを慮る気持ちがなければ価値は創造できないですよね。相手の人のためになって、その余剰が利益になってくる、例えば相手のために100円の価値を生み出せたら、そのうちの20円をいただきましょうというのがマーケティングですから、まさに「愛」という言葉で言い換えてもいいと思いますね。
蛭子 門外漢の私がいきなり「わらじプロジェクト」の経営でマーケティングを始めてしまいましたから、トライ・アンド・エラーの繰り返しです。このプロダクトはこうあってほしいと自身では思うのですが、お客さまやパートナー企業の方から「他にもこういう魅力があるよ」と自分では気づかない価値を教えていただくことがとても多いです。その辺りをうまく混ぜ合わせながら、遠回りをすることもありますが、何とか前に進めているという感じですね。
福島 例えば「わらじプロジェクト」では、藁は大事な資源だから駄目だと言われたわけですが、そのときになぜ諦めなかったのですか。どんな事業も最初に決めた通りにうまくはいかない。やってみると状況が違ってきて、事業もそれに合わせて形を変えていきながら最終的に一つの大きな事業として実を結ぶ、これはまさに事業開発時には非常に重要な要素だと思います。
蛭子 藁は駄目だと言われた以外にも沢山のピンチがありましたし、これからもきっと予期せぬ別のピンチが待っているのだろうと感じています。ただ、ピンチになったときに自分一人ではないという点はとても大きいです。一人だと、選択肢はもうこれしかないと思いがちですが、周りに複数の多様な考えの仲間がいて、Aが駄目ならB。Bで駄目ならC、Dといろいろな選択肢やアイデアを出し合って、その中から対話で選んでいくという繰り返しで今までやってきたように思います。仲間がいるからこそ、これまで幾度となくピンチを乗り越えてこられたのだと感じています。
福島 愛、一人ではない、対話で課題解決など、マーケティングの世界観をとても重要な言葉で語っていただきました。本当にそうだと思います。
福島 蛭子さんがホライズンの読者に一番伝えたいのはどのようなことですか。
蛭子 自分がホライズンで企画してきたテーマを振り返ってみると「土地の地力」「愛と美しさを信じ、守り抜く」「下目線」などで、かなり抽象的で好きなことを発信させていただいた印象が強いです。総じて「大切なものほど目に見えないから、それを感じ取って、一人ではなく皆で、少しでも良くしていきましょう」といったことがホライズンを通じて伝えたかったことだろうと思っています。
やはり、個人と社会はつながっていると思うので、自分も幸せ、近くの人も幸せ、間接的に携わった方も総じて幸せになっていったらいいなと思います。社会課題でも、例えば私自身も体験した待機児童の問題でも、昨日今日で生まれたことではなくて、今までの積み重ねかつ複雑な構造の中で社会問題化しているわけですよね。それを個人の課題や大変さに閉じずに、皆に開いて共有し、共感してもらって、どこをどうつなぎ合わせたらもっと良くなるかを一緒になって考えるのがスムーズだし、それこそデザインやアートの力なのだろうと思います。
福島 なるほど。デザインとコンセプトの違いは、コンセプトは必ず文字にするけれどもデザインは言葉に書けないことを伝えることができる。実はそのほうがずっと意味は深くて広いだろうと思うこともあります。
蛭子 そうですね。あるデザイナーさんから伺った話になりますが、その方が「色の印象として、“冷静さ”を伝えるためには赤より青のほうが使用されると一般的に思われているかもしれないが、使用するシーンによっては赤を選ぶこともあり得る。自分が赤だと考える理由を言語化して共感が生まれれば、赤で表現することはとても有効的だと思いますね」とおっしゃったことが印象に残っています。これまでの自分だけの経験や憶測で思い込まずに、そのときの状況や人の想いを汲み取って、それを表現して伝え広めるのがデザイナーの役目なのだろうと思いました。色選びと同じように、社会学も常識を疑う学問です。「当たり前を疑え」という基本的なところから学びが深まると思っています。
福島 ステレオタイプの判断で決めつけてしまったら新しいものは何も生まれてこないですよね。
福島 蛭子さんはバングラデシュの方々とお仕事されているわけですが、日本にいては体験できない違いがあるのでしょうね。靴を履いていない、電気が来ていないところもたくさんありますから、そういう現実を忘れないようにしたいですね。
蛭子 本当にそう思います。蛇口をひねればきれいな水が出てくる生活があることは、とても有り難いことですよね。「わらじプロジェクト」は創業時からフェアトレードの仕組みで運営しているのですが、あるとき学生が「そもそも、フェアトレードとは何ですか?」という質問をしてくれました。もちろん公式には「10の指針」というものはあるのですが、現地のパートナーの方は次のように教えてくださったのです。
「職人が明かりの足りている部屋で作業をしているか」「煮沸したお水を飲んでいるか」「家庭内でバイオレンスを受けていないか」などです。これは、日本人である私たちにとっては衝撃的な回答でした。要するに、物理的にも精神的にも、働く環境も人生も公私ともに心地よいかを定期的にお互いにチェックすることが大切だと経営者、そして働き手目線で教えてくださったのです。
そのような意味では、フェアトレードというのは自分たちが他国に対しての行為であると同時に、自国の社員など、関わっている人たちとの間でもフェアトレードを推し進めることが大切であることに気づかされました。その両輪で回していくことこそが真のフェアトレードだと感じます。
福島 社会課題とデザインというテーマで活躍してこられた蛭子さんはご存じかと思いますが、以前、日本マーケティング大賞(奨励賞)を受賞されたファッションブランドのマザーハウスさんは大変な努力をしつつ途上国支援をされている素晴らしい会社です。ブランドバッグほど高くないしデザイン的にもすっきりしていて、私の妻も大ファンなのです。その妻が言うのに、「心のきれいな人がつくったものはきれいに見える」と。ですから、社会課題やフェアトレードもそうですけど、そこには人々のいい念、善念というものがあるのではないか。この辺りがこれからのマーケティングにとって一番重要になってくるのではないかと感じますね。
蛭子 そうですね。人の心次第で良くもなるし、悪くもなってしまうのでしょうね。デザインを学ぶ上で「戦争とデザイン」の関係性についての本を読んだことがありますが、例えばヒトラーはアートやデザインが人を魅了するパワーをよく理解していたようで、制服デザインやしぐさなどビジュアルもトータルで考えられていて、その力で大衆が動いてしまった側面があると知りました。大衆の心をつかんで動かしてしまうほどの力のあるデザインやマーケティングという手段を、どのように使って皆がいいと思う方向に持っていくかがとても大切だと感じます。
福島 コトラーさんも「コモングッド(Common Good)=共通善」と言っていますが、これも蛭子さんがおっしゃる“皆がいいと思う方向”という意味ですよね。私は先ほど善念という言い方をしましたが、そういうものがマーケティングの中で定着して当たり前のことになってくれるといいと思います。
蛭子 そうですね。“皆がいいと思う”ということは“それぞれの意見”を交換し合った土台の上に成り立つと感じています。それは、以前ホライズンでも取材させていただいた社会学者である上野千鶴子さんのお話の内容を思い出したからなのですが、上野さんから「他人の言うことに100%同意することはありません。一部は同意するが、他の部分には同意できない。そうやって議論を詰めていくところから、次の一歩が生まれます。日本のゼミでは、質疑応答が一問一答で終わってしまいがちです。すれ違ったまま、飲み込んで黙る習慣があるようです。きちんとかみ合う会話になっておらず、互いの意見が、双方に影響し合う経験があまりないようです。(抜粋)」というお話をいただきました。
その流れでさらに「ネガティブ・ケイパビリティ」という詩人ジョン・キーツの言葉がありますが、AとBが違うときに諦めるのではなく“耐える”、そして“保留する”力を持って考え続けようという態度のことです。まさに上野さんがおっしゃっていることと通ずる部分があると感じます。誰でも自分とは異なる意見を聞くことや摩擦は避けたいことではありますが、社会皆で生きている限り避けては通れないことです。日本はとても豊かで精神的にも文化的にも素敵な国と国民だと思うので、これからも未来につなげていけるように対話を育んでいきたいですね。
福島 私も本当にそう思います。本日はありがとうございました。
思想家・安岡正篤は知識、見識に加え、困難な事態に突き当たっても、あらゆる抵抗を排して断固として自分の思うところを実践に移していく力を「胆識」と説いています。この胆識とは強く激しいものではなく、明るく朗らかでこれほどまでにしなやかなものであるということを、蛭子さんに教えてもらいました。誰かのために価値を創り出し社会に貢献していくことがマーケティングであれば、まさにそれを自然体で体現し続けていると言えるのではないでしょうか。インタビューは、とてもさわやかな時間でした。

蛭子 彩華(えびす あやか)
MARKETING HORIZON 編集委員
一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事
クリエイティブデザイナー
1988年群馬県前橋市生まれ。2012年立教大学社会学部を卒業し、IT企業に勤務。
結婚を機に退職し、夫の南米チリ駐在へ帯同。帰国後の2016年、第一子出産と同時にTEKITO DESIGN Labを設立。
現在は3児の母として、様々な社会課題に、デザインとビジネスの循環の仕組みでアプローチしている。2025 年 11 月からは再びチリ駐在に帯同し、日本の裏側から距離や境界を越えて人と社会をつなぐ働き方と表現の可能性を探っている。
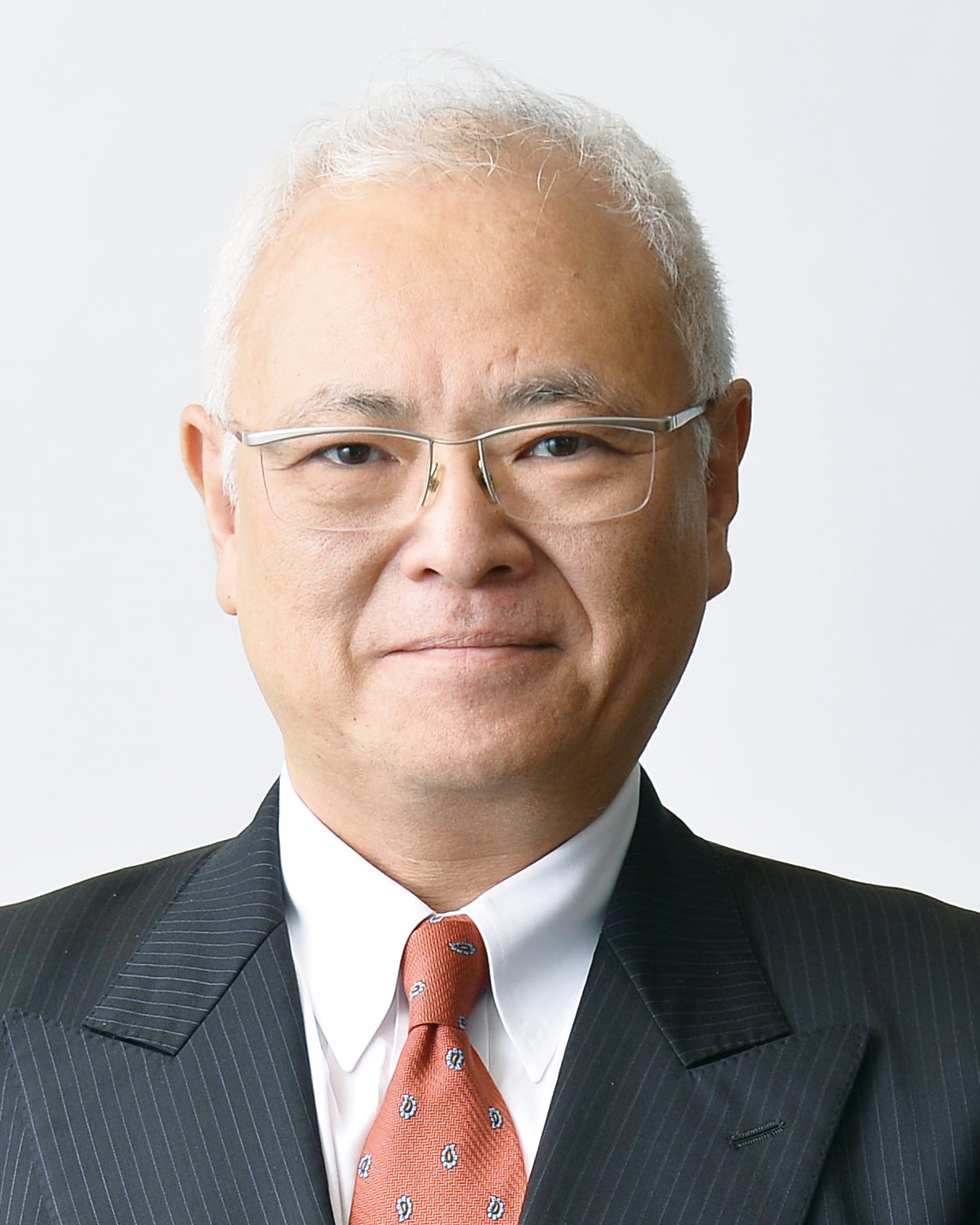
福島 常浩(ふくしま つねひろ)
MARKETING HORIZON 編集委員
株式会社AEOS 取締役
味の素で20年近くマーケティング関連業務とIT関連業務を担当、その後GEにて生保のネット販売事業の立ち上げ、三菱商事にてID-POSビッグデータ事業の立ち上げ、ぐるなびにて事業拡大と東証1部上場、メディカル・データ・ビジョン株式会社にて医療情報の活用事業の立 ち上げに参加し東証1部上場。その後トランス・コスモス株式会社を経て現職。
新規事業・新商品の立ち上げを多く経験。
日本マーケティング協会理事およびマーケティングマイスター
一般社団法人市場創造学会 代表理事・副会長
アルゴマーケティング研究所合同会社 代表社員
Interviewee
山本 裕介
MARKETING HORIZON 編集委員
エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
Interviewer
蛭子 彩華
MARKETING HORIZON 編集委員
一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事
クリエイティブデザイナー
「コミュニケーション」を仕事の軸に据えた働き方、そして生き方をされてきた山本裕介さん。そんな山本さんの足跡を追いながら、地道で緻密なマーケティング活動の裏側や、人間味あふれる広い視野から生まれる「人」への想いをうかがいました。
蛭子 山本さんは、圧倒的な情報処理の速さ、人とすぐに打ち解けられる笑顔が印象的で、軽やかに変化しながら周囲をリードするパワフルな方だなと常々思っていました。まずは、そんな山本さんの生い立ちをお聞かせいただけますか。
山本 そう言っていただきありがとうございます。私は、1980年に広島の宮島の近くで生まれ、両親とも地方公務員の家庭で育ちました。小中学校時代は、祖父母が広島の目抜き通りで営んでいた靴屋を手伝いながら、週末は母方の家があった瀬戸内海の島で釣りをするという生活でしたね。中高は男子一貫校だったのですが、この6年間が人生の暗黒時代だったなと感じています。
蛭子 暗黒時代とは、とても意外でセンシティブなワードですね。具体的なお話をお聞きしてもよろしいでしょうか。
山本 実は、当時の私は人とコミュニケーションを取るのが得意ではなかったのです。その頃、人の輪の中に入っていったり、まして集団をリードしたりするようなことはほとんどできていなかったですね。そんな暗い時代を経て大学進学のために上京し、それからはずいぶん人とコミュニケーションが取れるようになりましたが、4年生になってからの就職活動では内定をいただけずとても苦労しました。卒業論文を書く際に、自分が苦手としていた「コミュニケーション」に向き合ったことで広告に興味関心が高まり、5年生にしてやっと広告代理店から内定をいただきました。
蛭子 ご自身でもコミュニケーションの課題を抱え、しかしそこから目を背けずに見つめ直したのですね。
山本 そうですね。例えば「人は10代のときに苦しんだことに一生こだわり続ける」と言われたりしますよね。お金で苦労したら、その後もずっとお金にこだわる人になるなど。私の場合はコミュニケーションにつまずいたので、逆にコミュニケーションにものすごくこだわることを仕事にしたのでしょうね。
広告代理店に就職し、営業担当をしていた頃も、コミュニケーションに強みがあるタイプではありませんでしたが、得意先に可愛がっていただける環境に恵まれました。その頃、SNS系に特化した新会社をデジタルガレージなどと合弁でつくる立ち上げメンバーとして出向し、当時の食べログの事業化を担当しました。その後、2009年には Twitter(現:X)を日本展開するプロジェクトに参画し、Twitter日本版の立ち上げに携わるようになりました。
Twitterは日本で当初、マンスリー・アクティブユーザーが約30万人程度でしたが、2009年から2011年で約1,500万人まで拡大しました。わずか2年で50倍も拡大するサービスはそれまでなかったと思います。その凄まじい成長を間近で見届けられて本当に仕事が楽しかったですし、何よりそこで初めてマーケティングに触れることができました。
例えば、バリュープロポジションやユーザーにとってのサービス価値をチームで考えたり、ユーザーをセグメントしながら、コンテンツパートナーシップを通じて新しいユーザーとの接点づくりに取り組んだりしました。そうした試行錯誤の中で、マーケティングの基礎的な考え方について実感を持って学べたように思っています。
また、自身のアイデアから「ツイナビ」というTwitter公式の日本向けガイドサイトを立ち上げ、企画から運用までを数人で担当しました。アカウントのフォロワー数をゼロから約50万人規模まで育てることができたのは、非常に貴重な経験でした。
しかし、2011年3月に起きた東日本大震災をきっかけに、物事の捉え方が大きく変わりました。リアルタイムでローカルな情報を届けるツールの重要性を改めて感じる一方で、自分自身の仕事へのモチベーションは、より長期的でもっと多面的なかたちで社会に関われることへと少しずつシフトしていきました。
蛭子 そういった経緯から、Googleへの転職につながったのですね。
山本 そうですね。英語はあまりできませんでしたが、YouTubeやGoogleマップをはじめとする多彩なサービスが、人々の生活や社会を確実に変えていく姿に強く惹かれていました。「ここで働くことで、世界とつながる仕事ができるかもしれない」──そんな想いから、自分の可能性を信じて応募しました。英語での面接では、言葉だけでは伝えきれない気持ちや考えをパワーポイントにまとめ、プレゼンテーションというかたちで表現しました。その姿勢や覚悟を評価していただけたのだと感じています。
入社後は、まずプロダクトマーケティングを担当し、その後、コーポレートブランディングへと役割を移しました。日々の業務の中で常に意識していたのは、日本社会が抱える課題と、Googleの技術や思想をどう結びつけられるのか、という問いでした。単なるブランド発信ではなく、社会と誠実につながるあり方を模索し続けていました。
2014年からは、「Women Will」というプロジェクトを立ち上げ、女性も男性も誰もが働き続けやすい社会をつくるため、延べ1,000社以上のパートナー企業・団体と社会に対しての提言を行いました。2017年からはデジタル人材育成を担当し、デジタルスキル支援プログラム「Grow with Google」を通じて、延べ1,000万人に無料トレーニングを届けることができました。2020年頃からは、リスキリングやAIといった新しいテーマにも向き合い、コロナ禍といった大きな変化の渦中にいる人たちにどう伴走できるかを考え続けるようになりました。
こうした仕事の流れとは別に、入社直後から私自身の価値観を大きく揺さぶった東日本大震災に関するプロジェクトにも取り組んでいました。「未来へのキオクプロジェクト」は、今でも深く心に残っています。被災地で撮影された写真や動画、一人ひとりの体験談といった“記憶”を残し、見えるかたちにすることで、それらを復興の力や学びにし、そして未来へと手渡していきたい──そんな切実な思いから生まれた取り組みでした。
蛭子 山本さんが大切にされていることを、会社という組織を通じて、社内そして社会へと着実に実装されていかれたのだなと強く感じました。
山本 Googleのミッションは、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスして使えるようにすることです。正確で多様な情報が手に入れば、人はより良い判断ができるようになり、結果として世の中は良くなっていく。私は今もその考えを信じています。一方で、Googleでのキャリアが10数年経った頃、次第に「自分が人生をかけて本当に大切にしたいものは何なのか」を考えるようになりました。その答えは、情報や仕組み以上に、「人そのもの」だったのだと思います。自分の中にある「人間観」を見つめ直すために、まずは自分自身と向き合い、同時に、さまざまな人生を歩んできた諸先輩方との対話を重ね、最終的に今の人材業界の会社へ転職する決断をしました。
これまでのキャリアでも事業開発や経営企画という仕事は行っていましたが、CEOという立場は初めてやらせていただくかたちになります。ただ、これまでのキャリアを振り返ると、常に同じ状況からのスタートでした。マーケティングの経験がなかったときも、英語が話せなかったときも、不確実さの中で一歩踏み出し、前に進んできました。そうした経験があるからこそ、今回もまた学びながら進んでいけると考えています。
私がこれから最もやりたいことは、何かを変えたいと思っている志ある方々をお繋ぎすることです。特定のカテゴリーの企業様や候補者様に閉じるのではなく、より広い視点で多様な企業と人を支え、挑戦する人を一人でも増やし、その積分として、社会をより良くしていきたい。そんなふうに考えています。
蛭子 ご自身が本当に納得できるまで対話を大切にし、そのプロセス自体を仕事に重ねながら、自然なかたちで社会へ価値を返してこられていると感じます。
山本 ありがとうございます。AIによって物事を行うコストが劇的に下がった先にある世界では、「何がやりたいか」ということがとても重要になると思っています。「何ができるか」ではなく「何がやりたいか」「どのような社会や世界を望むのか」という「人の意志」ですね。人材業界の仕事は、まず「あなたは何がやりたいのですか」と問いかけるところから始まります。だからこそ、人と人の対話、つまりコミュニケーションを根幹に据えた、非常に重要な仕事だと感じたのです。
蛭子 AI時代だからこそ、人とのコミュニケーションがさらに重要になってくるのですね。話は変わりますが、山本さんにとってマーケティングとはどのような存在なのでしょうか。また、『マーケティングホライズン』に編集委員として関わる中で、どのような学びや気づきを得られましたか。
山本 マーケティングとは「人の心を動かすこと」そのものである、ずっとそう思ってやってきました。日々、手に取るコーヒーも、それこそ転職もそうですが、結局、人の心が動かないと何も起こりません。人の心を動かすために、どのようなタイミングで、どのようなメッセージを、どの媒体チャンネルで出すのかを考えること、つまり、プロフェッショナルが行うすべてがマーケティングだと捉えています。
編集委員の経験はとても楽しかったですし、マーケティングとは私が思っているよりもかなり広い概念なのだと感じましたね。「そもそも今はどういう時代で、何が求められているのか」といったような抽象度の高い話も、多様なバックグラウンドをお持ちの皆さんと議論できたことが非常に面白かったです。
実際、自分が経営をやってみるとよくわかるのですが、狭義のマーケティングは、日々のセールス活動に近い立ち位置にあると思います。一方で、より広い意味でのマーケティングは、「今はどんな時代なのか」「人は何を求めているのか」「これから社会はどうなっていくのか」といった問いに向き合うことです。そう考えると、それは経営そのものだと言えるのではないでしょうか。狭義と広義、どちらのマーケティングにもそれぞれの価値があるのだと思います。
もう一つ、マーケティングについて感じていることがあります。現在働いている会社は、約26年の歴史を持ち、規模もそれなりに大きいです。その分、多くの変遷を経てきましたし、社内には本当に良いものがたくさんあります。ただ、それらの価値をきちんと見つけ出し、「価値」として社員や社外に十分に伝えきれていないと感じる場面もあります。
改めて考えてみると、良いものを見つけ、その中にある魅力や要素を言語化し、わかりやすく伝えること自体がマーケティングなのだと思います。そうした視点を持つ存在だからこそ、マーケターは経営者になるべきなのではないかと。最近は、そんなふうにも考えていますね。
蛭子 山本さんが『マーケティングホライズン』を通じて読者に最も伝えたかったことはどのようなことでしょうか。
山本 一言で表すのは難しいですが、自分のキャリアを振り返ってみると、常に「テストマーケティング」を繰り返してきたように思います。結局やってみなければわからないわけで、言わばお試し的な考え方ですね。たくさんの小さなテストマーケティングを何度もやってみて、どこに合うかを見定めていく。広い意味でのマーケティングとは、物事を実行するハードルを低くして、仕事そして自分の人生をより面白くできるような方向を考えていく思考法なのかもしれません。
そうした考えから、読者の方にも「最初から正解を求めなくていい。まずは小さく試してみてほしい」ということを伝えたかったのではないかと思います。テストマーケティングを重ねる中でこそ、自分なりの道や納得できる選択が見えてくるのではないでしょうか。
蛭子 確かにテストマーケティングだと考えると、何だか肩の荷が下りて動きが軽くなるような気持ちがしますね。「ホップ、ステップ、ジャンプ」の流れではなく、「ホップ、ホップ、ホップ」の連続があり、気づいたらもうジャンプしていましたといった感じでしょうか。
山本 まさに「ホップ、ホップ、ホップ」という考え方は、人生のあらゆる場面に当てはまるのかもしれません。振り返ってみると、プライベートでも数えきれないほどのホップがありました。国内に限らず、さまざまな国へ何度も引っ越してきたため、子どもたちもそのたびに転校を経験しています。けれども、子どもたちの様子を見ていると、「ホップ」に対する心理的なハードルが驚くほど下がっていることに気づかされます。「次はどこに行きたい?」と聞いても、「別にどこでも大丈夫だよ」と返ってくる。その柔軟さに学びを得ることも多いですね。
ちょうど2026年1月から、Business Insider Japan様で、親子で国内15ヶ所の子連れリモートワークを体験したあと軽井沢に家族で移住し、さらに子どもたちがマレーシアに留学したという我が家の冒険を寄稿させていただく連載を始めました。
記事/



英語には「There is no silver bullet(銀の弾丸のように、物事を一気に解決する方法はない)」や、「Test the waters(とりあえず足を水に入れて確かめてみる)」という表現があります。プライベートでも仕事でも、まさにそんな感覚でテストマーケティングを続けていく中で、少しずつ自分なりのキャリアがかたちづくられ、それに伴ってマインドも変化し、成長してきたのだと思います。これまでそうして歩んできましたし、きっとこれからも変わらず、その姿勢で進んでいくのだろうと改めて感じました。
蛭子 本日は、とても軽やかでありながら力強い示唆をいただき本当にありがとうございました。これからも山本さんの数々の「ホップ」のお話を伺えることを、今からとても楽しみにしています。私自身も、テストマーケティングの視点を持ちながら、どこにいても前向きに歩んでいきたいなと思いました。今後ともよろしくお願いいたします。
山本さんのお話から感じたのは、人は試しながら学び、他者との対話を通じて仕事、そして人生をより豊かな方向へ成長させていける存在だという強い信念でした。テストマーケティングを続ける姿勢は、失敗や遠回りさえも、自分をかたちづくる大切でかけがえのない「ホップ」と、前向きな視点を与えてくれます。試し、対話し、また試す。その積み重ねの先にこそ、自分なりの心地よい人生が立ち上がってくるのだと気づかされました。

山本 裕介(やまもと ゆうすけ)
MARKETING HORIZON 編集委員
エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
大手広告代理店で経験を積んだ後、Twitter日本上陸時のマーケティング・広報を担当。その後、Googleにて日本市場でのコーポレートブランディングや、テクノロジーを活用した社会課題解決プロジェクトに従事。現在はエンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長を務める。

蛭子 彩華(えびす あやか)
MARKETING HORIZON 編集委員
一般社団法人TEKITO DESIGN Lab 代表理事
クリエイティブデザイナー
1988年群馬県前橋市生まれ。2012年、立教大学社会学部を卒業し、IT企業に勤務。
結婚を機に退職し、夫の南米チリ駐在へ帯同。帰国後の2016年、第一子出産と同時にTEKITO DESIGN Labを設立。現在は3児の母として、さまざまな社会課題に、デザインとビジネスの循環の仕組みでアプローチしている。2025年11月からは再びチリ駐在に帯同し、日本の裏側から距離や境界を越えて人と社会をつなぐ働き方と表現の可能性を探っている。
Interviewee
帆刈 吾郎
MARKETING HORIZON 編集委員
博報堂生活総合研究所 所長
Interviewer
山本 裕介
MARKETING HORIZON 編集委員
エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
聞き手の山本氏も広告会社の出身であることから、本回は、博報堂生活総合研究所所長の帆刈吾郎さんに、広告産業の魅力やクリエイティビティの特性、これから求められるであろう新たな役割や方向性などについてうかがいました。
山本 この時代における広告会社の役割に、強い関心を持っています。近年は、コンサルティング領域への進出や、AIを多様な業務に活用する動きが加速しています。そのような変化の中で、広告代理店が最も価値を発揮できる領域はどこにあるのか、考える機会が増えています。
そこでまずお聞きしたいのは、広告代理店の将来像といった大きな話ではなく、より一般的な意味での広告や広報が、今後どのように変化していくのかという点です。
帆刈 難しい問いですが、産業の再定義が必要だろうと思います。これまでは広告産業と考えられてきましたが、今後はクリエイティブ産業と捉え直す必要があるのではないでしょうか。ここで言うクリエイティビティとは、アイデア出しや広告制作といった狭義の話ではなく、「創造性」という意味合いです。従来の広告業が有してきたケイパビリティや提供価値の源泉は、突き詰めると「創造性」にあると考えているからです。
創造性が求められる領域は、もはや広告に限らず、かなり広いフィールドに及ぶと考えます。例えば、顧客獲得を目的としたマーケティングコミュニケーションだけでなく、社内の組織開発に関わるインナーコミュニケーションの領域もあります。
社員の意欲を高め、また「この会社で働きたい」と思ってもらうためには、社員や求職者の心がわくわくするなど何らかの形で動く必要があります。形式的で通り一遍の表現では、その思いは伝わりません。そこには、広義の創造性が要求されるのではないでしょうか。
山本 クライアントに高度な専門サービスを提供することや、実際の考え方や施策を社会に発信し、新たなケイパビリティを啓発していくことも創造性の1つと捉えられますね。
帆刈 そのような創造性はどこから生まれるのかというと、もちろん個人のひらめきによる部分もありますが、それ以上に重要なのは、世の中の変化や生活者の感覚など、業界の常識や企業人としての枠組みにとらわれない視点を、どれだけ自分の中に持っているか。そうした感覚こそが、創造性の源泉になると考えます。
この観点で言えば、ビジネスにおける創造性とは、企業人としてではなく、1人の生活者としての感覚や視点、すなわち生活者発想を重視する姿勢からも生まれます。
山本 創造性は、例えば岡本太郎といった一風変わったアーティストのような方が持つものであり、日常生活からかけ離れていることが創造性の源泉だというような空気感もかつてあったように思います。
帆刈 いま私は、「生活知」という言葉をつくり、その重要性を提唱したいと考えています。もちろん、業界の知識やテクノロジーの知見などの重要性はいうまでもありません。一方で企業のこれからの意思決定においては、世の中の変化に対する知見も必要です。生活者の洞察から世の中の変化を読み解く知見を「生活知」という言葉で定義し、「生活知」がこれからのビジネスにおいて重要だということを提唱していきます。宣伝やマーケティングコミュニケーションに携わる人に限らず、あらゆる企業人にとって新たな価値を生み出す源泉として「生活知」の重要性と具体的な研究成果を広めていきたいと考えます。
山本 地に足がついた視点で、さまざまな人の暮らしをきちんと想像できること、そしてそれを理解していることが、創造性につながるということですね。
帆刈 そうですね。この業界の常識はこうだとか、新しいテクノロジーが出たら取り入れ、企業は同じ方向に向かいがちですよね。しかし、皆が同じように進んでいく中で、どうやって差異を生み出すのか。同質化・均質化が進む一方、企業の独自性や競争優位性をどこに見出すのかが問われています。もちろん手掛かりとして、テクノロジーの優位性を追求するというやり方もありますが、それだけでなく、企業視点から脱して生活者視点を持つこと自体が、大きな競争戦略であり差別化につながるのではないでしょうか。

山本 帆刈さんがおっしゃる、他者の視点を取り入れることやそのための生活知が創造性を高めるという点は、非常に興味深いと感じました。突き詰めれば、マーケティングとはそういう営みなのかもしれませんね。
帆刈 それは私なりのマーケティングの定義とも関わってきます。マーケティングを、単にビジネスの一機能や「何かを売る行為」と結びつけて考える必要はないと思っています。実際、物を売らない公共サービスの分野でも、マーケティングの考え方は必要とされています。マーケティングとは何か。それは、何かを売るビジネスと紐付いたものではなく、「自己中心に陥らず、普遍的に他者の意見や視点を取り入れることで、やろうとしていることの成功確率を高める行為」であると思っています。
マーケティングを社会全体にとって意味のある行為として定義し直せば、より良い社会や、より良いコミュニケーションを生み、相互理解を深めることにつながるのではないかと思います。
山本 そのためには多様なものの見方や考え方を取り入れ、創造性を高めていく必要があるということでしょうか。
帆刈 多様性が高まるほど創造性も高まるという相関関係は確かにあると思います。外部の視点を取り入れることで物事をより俯瞰して捉えられるようになり、その結果として、人の心を動かすマーケティングや、より創造的な取り組みにつながっていくのではないでしょうか。
山本 以前の広告会社には、こういう価値を世の中に届けたい、こういう世の中にしたい、こうなっていくべきだと強い世界観を持つ人が多かった印象があります。そうした姿勢はいまも残っているのでしょうか。
帆刈 確かに以前は、時代をつくる、トレンドをつくるといった意識を強く持つ人が多かったように思います。自分が先頭に立って時代を創造し、切り拓いていく、というタイプの人たちですね。
一方で現在は、「センス」に加えて「センシティブ」であることも重視されている印象があります。広告業の人は、新しい生活者の意識や社会課題に敏感だ、あるいはそうありたいと考える人が増えているのではないでしょうか。
広告業界に限らず、スタートアップなども含めて「社会課題を解決したい」と考える人が増えています。特定の課題を1つの事業で解決したいのであれば、社会課題解決型のスタートアップを選ぶかもしれません。一方で、より幅広い社会課題に向き合い、複数のプレーヤーと組みながら取り組みたいと考える人が広告会社を志向するケースもあるように思います。そうした人たちは、社会や生活者の変化に対する感度を大切にしている印象があります。
山本 そのような感度を持ち、社会課題の解決に貢献したいと考える人が集まってくるということでしょうか。
帆刈 それも1つの側面だと思います。もう1つ、広告会社ならではの特徴として、「ビジネスとカルチャーを横断する仕事がしたい」と考える人がいる点が挙げられます。カルチャーとは、例えばスポーツやアート、エンターテインメント、コンテンツといった領域です。これらの分野にはそれぞれ多くの担い手がいますが、それらとビジネスを結びつけ、価値として成立させる役割、いわば橋渡しを担えるのは広告会社ならではだと思います。
山本 帆刈さんご自身は、なぜ広告業界を選ばれたのでしょうか。
帆刈 先ほどのビジネスとカルチャーの架け橋という点は、実は自分自身の動機とも重なります。
私はカルチャーだけでなくビジネスにも関わりたいという思いがありました。その点で、広告会社は両者のバランスが取れていると感じたのだと思います。
また、ものづくりに関わる人は「良いものをつくれば自然と広がる」と考えがちですが、私は、良いものであればあるほど、きちんと広く伝えるべきだと感じていました。振り返ってみると、つくる側というよりも、「良いものを世の中に届ける側」に強く惹かれていたのだと思います。

山本 伝えるという点で言うと、日本の教育には、人に伝える方法を体系的に学ぶ場がほとんどないことが課題だと感じています。そもそも、みんなそんなに相手に関心がありません。特に自分がいた外資系企業の仕事を思い返しても、海外のカンファレンスなどでは、話し手がどれだけ熱心でも聞き手は席を立ったり、コーヒーを取りに行ったりします。そのような場を何度も経験してきた立場からすると、「どうすれば人に聞いてもらえるのか」を誰も教えない教育は危ういと思います。
振り返れば、中学や高校でも、校長先生の話が退屈で注意された経験がありますが、「話がつまらないこと自体が問題だ」という視点は存在していませんでした。校長先生自身も含め、誰も「伝え方」を系統立てて学んできていないのです。だからこそ、「伝える技術」という観点で、マーケティングを一度は必修として学ぶ価値があると思います。
帆刈 まさにその通りで、教育の中で「何をどう伝えるべきか」をもっと考える必要があります。話し方の工夫といった表面的な技術もありますが、それ以前に大切なのは、何のためにプレゼンをするのかという点をしっかり考えることです。例えば、「自分の好きなものを伝えたい」という場合、それは何のためなのか。それを実現するにはどうすればよいのか。説明するだけでなく、実際に触ってもらう、見せるといった作戦も考えられます。目的から考えれば、伝える手段は自然と変わってくるはずです。
そう考えると創造性とは、そもそもの前提に立ち返って考えることなのかもしれません。私たちは「どうやるか」というHowの問いを与えられすぎている気がします。本来は、「なぜそれをやるのか」「何を実現したいのか」というWhyの問いに一度戻り、そこから改めてHowを考える必要があるのではないでしょうか。それが創造性とも関係していくのではないでしょうか。
山本 確かに、創造性とは本来の理由を問い直すことなのかもしれませんね。Whyを深く掘り下げれば掘り下げるほど、Howの選択肢はいくらでも広がっていきます。
この話を聞いて思い浮かぶのが、Googleにおける10X(10倍)です。10%の成長であれば、従来の延長線上のやり方で誰でも対応できます。しかしこれが10倍の成長となった瞬間、同じ方法では通用せず、違うことを考えなければなりません。市場や事業を実際に10倍にしようとするには、そもそもなぜこれをやるのかという「Whyの問い」が必要になってくるのではないでしょうか。
帆刈 10Xの話は象徴的ですね。来年の予算は7%増ですと言えば、今の延長線上で頑張ろうという発想になりますが、10倍ですと言われたら、前提をすべて疑わざるを得ず、ゼロベース思考ですよね。やり方もゼロから変えないと無理だ、となりますよね。従来のやり方を改善するだけでは到底届かないゴールですから、根本的な発想転換を迫られるわけです。
山本 まさにそうですね。もちろん、言うは易く行うは難しだと自分でも感じていますが、本質的には非常に大事なことですよね。
本日は大変勉強になりました。ありがとうございました。
帆刈さんがおっしゃった「センスがある人ではなくセンシティブな人」というお言葉が印象的でした。センスといういわば独善的で個に閉じた力ではなく、時代やそこで生きる人々のリアリティや生活にセンシティブさを持てる人こそが、社会を的確にとらえて変えていくことができる、メッセージをより届けることができる、という観点は今後ずっと大切にしていきたいと思いました。

帆刈 吾郎(ほかり ごろう)
MARKETING HORIZON 編集委員
博報堂生活総合研究所 所長
1995年に博報堂入社、以来マーケティング職に従事。2013年タイ・バンコクに駐在、博報堂生活総合研究所アセアンを設立。2020年日本に帰任し現職。

山本 裕介(やまもと ゆうすけ)
MARKETING HORIZON 編集委員
エンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
大手広告代理店で経験を積んだ後、Twitter日本上陸時のマーケティング・広報を担当。その後、Googleにて日本市場でのコーポレートブランディングや、テクノロジーを活用した社会課題解決プロジェクトに従事。現在はエンワールド・ジャパン株式会社 代表取締役社長を務める。
Interviewee
ツノダ フミコ
MARKETING HORIZON 編集委員長
株式会社ウエーブプラネット 代表取締役
Interviewer
帆刈 吾郎
MARKETING HORIZON 編集委員
博報堂生活総合研究所 所長
長年、編集委員を務め、2022年より編集委員長に就かれたツノダさん。インサイトの導き出しやコンセプト開発を手掛けるキャリアの原点は、意外にもご自身の「コンプレックス」にあったと語ります。データやAIが進化する現代において、マーケターが提供すべき本質的な価値とは何か、そして政治家として活動された経験が現在の視座にどう繋がっているのかをうかがいました。
帆刈 まずは、ツノダさんがこの道に進まれたきっかけを教えてください。
ツノダ もともと私は、自分のことを「傍観者」だと感じていました。物事の輪の中になかなか入れず、どこか一歩引いて見ている。それが長らくコンプレックスであり、自分の弱みだと思っていました。
ところがある時、傍観者であるがゆえに頭の中に溜め込んでいた様々な景色や情報が、初めて役に立った瞬間というのがあったのです。クライアントや上司が口頭で話す「これこれ、こういうことなんだよ」という言葉や、世の中の事象、人々の価値観、時代のニーズといった、一見バラバラな要素を、頭の中で整理して一枚の図に表してみたのです。
自分にとっては苦でもない作業だったのですが、それを見た上司やクライアントから「すごくわかりやすい」「そうそう、こういうこと!」とても喜んでもらえたのです。その時、「ああ、こういうことをありがたがってくれる人たちがいるんだ」と初めて知りました。私のライフワークというのはこれなのか、と気づかされる経験でした。
帆刈 では、この仕事を長く続けられた原動力は何だったのでしょうか。
ツノダ もちろん、褒められると嬉しいですし、人の困りごとを解決できた感覚もありました。ですが、私にとって一番大きかったのは「繰り返しが一つもない」ことでした。私はめちゃくちゃ飽き性で、繰り返しが苦手なんです。その点、この仕事は毎回違う課題に向き合える。それがありがたかったですね。
帆刈 30年以上続けられる中で、求められる役割に変化はありましたか。
ツノダ 面白いことに、本質は大きく変わっていないと思います。一見、複雑に絡まっているように見えるものを一つ一つほぐし、もう一度わかりやすく組み立て直す。その部分が求められていることに変わりはありません。
ただ、最近はテクノロジーが進化し、データをパパッと整理したり、一瞬で構造化したりすることはAIでもできるようになりました。その分、より「根源的な部分」へのニーズが高まっていると感じます。
帆刈 根源的な部分、と言いますと?
ツノダ 例えば、ビッグデータのように表面的なデータは誰もが手にできるようになりました。だからこそ、その奥にある「本当の人間の気持ち」や「インサイト」への深掘りが求められています。
AIを使うことはもはや前提というか当たり前になっています。クライアントもAIを触っていて、表面的な理解はできている。AIは一聞いたら百ぐらい返してくるので、情報はいくらでも手に入ります。しかし、「それはわかったけど、要するに?」という部分においてAIが出してきた答えではもう一つしっくりこない、どうも「腹落ちしない」のです。
AIは責任を取りませんし、唯一絶対の答えも出してくれない。だからこそ、AIが提示した答えを解釈し、読み解き、「要するにこういうことです」と提示する。そして、「これで決断してもいいんだ」という安心感や、「覚悟を決める言葉」を提供する。これこそ人に求められる役割であり、このニーズはますます強くなっていると感じます。
帆刈 それは、ロジックを超えた価値ですね。
ツノダ そう思います。多分、その言葉以上に「この人が言ってくれたから」という、信頼関係の部分も大きいのではないでしょうか。お互いに信頼しあって議論できる関係があってこそ、提供できる価値なのかもしれません。
帆刈 その「根源的な部分」や「腹落ち」に迫るために、独自のアプローチや手法をお持ちですか。
ツノダ もし確立された手法があれば、私もそれを水平展開してもっと儲けられているのではないかと思いますが、ないんですよね(笑)。ただ、無意識に、癖としてやっているのは「自分ごと化する」ということです。それはすごくあります。「自分だったら」とか、「うちだったら」とか、自分のこととして考える。
帆刈 具体的には、どのように「自分ごと化」されるのですか。
ツノダ 例えば、「もし自分がお客さんだったら」というのはもちろんありますし、「もし自分がこのプロジェクトを任されたら」とか、「こういうことを上司に頼まれたら」などクライアントさんの立場に立って考えることは当然あります。生活者インサイトも大事ですが、クライアント・インサイトについてもかなり考えます。
ただそれだけでなく、世の中のありとあらゆること、例えば、お買い物に行った先の販売員の方の立場だったらどう考えるか、あるいは、「ここのオーナーだったらどう考えるかな」など。常に多視点を自分のこととして捉えるようにしていますが、これは無意識の癖のようなものですね。自分ごと化して傍観しているのかもしれません。
帆刈 なぜ多視点を得るためにツノダさんのような外部の役割が必要なのでしょうか。
ツノダ クライアントの方というのは、それこそ数字を背負っていたりして、ご自身の責任や役割、求められていることがガチっとあるわけじゃないですか。胃が痛くなるようなそういう環境にいらっしゃると、目の前の課題や事業に集中しすぎて多角的な目線は持ちにくくなってしまうんだろうな、と感じます。
だからこそ、外部にいる私たちがそうした目線を提供することに価値を感じていただけている。期待されている部分としては、そういうところがあるように感じますね。
帆刈 キャリアの途中で、一度政治家(市議会議員)も経験されています。これはどのような思いからだったのですか。
ツノダ 実は、中学生の頃の夢が政治家になることだったんです。当時はまだ、学校の家庭科が男女別々でした。私はそれが「おかしい」と強く感じて。なぜ国が、男の子は日曜大工やはんだ付けで、女の子はお裁縫や料理をやることを強いるのだと。それを義務教育としてやるのはおかしい、と。
それで私は家庭科の授業をボイコットしたり、校内の弁論大会でそれを訴えたり、新聞に投書したりしていました。その時、私は絶対政治家になるな、と思っていたんです。まあ、典型的な中二病のようなものでしたが。
帆刈 その夢が、47歳で実現したわけですね。
ツノダ 高校、大学と遊び呆けて、そんなことはすっかり忘れていたのですが(笑)。 47歳の時、 ちょうど政権交代があり、 「世の中が変わるかもしれない」「もしかしたら私にもチャンスがあるかもしれない」とかつての夢を思いました。ちょうど政治家の「公募」が始まった頃で、応募したのがきっかけです。
帆刈 理想と現実のギャップは、ありましたか。
ツノダ もう、大いにありました。とにかく痛感したのは、お役所も議員も、どちらも「前例主義」だということです。
例えば行政だったら、予算をどう使うか。その使った予算配分が正しかったのかどうかに基づいて、次の年の予算を考えなければいけないのに、そこでのPDCAが、P(計画)もC(評価)もほぼ機能していなかったのです。毎年D(実行)で完結し、その繰り返し。前年と同じことが重視され、根拠も検証もなされていないことに驚きました。
帆刈 まさにマーケティング的な視点が欠けていたのですね。
ツノダ そうなんです。もう一つ感じたのが、生活者の声の扱いです。各政党・会派は当然のことながら自分たちの支援者の声に応えようとします。しかしそれだけではなく、いわゆる「サイレントマジョリティ」の声、あるいは本当に困っているけれど声を上げられない人たちの声をどうやってちゃんとすくい上げて、市政に反映していくか。その仕組みをきちんと作らなくてはいけない、という提案をしました。これはもう100%マーケティングですよね。
その他にも、市のブランディングへの取り組みや、「シビックプライド」という概念を提唱して、それを中長期計画に盛り込んでもらうといった活動も行いました。
帆刈 政治家としての経験は、マーケティングの仕事にどう影響していますか。
ツノダ それは非常に大きな影響がありました。一つは、議員になる前には見えていなかった世界、「格差が拡大する世界」を目の当たりにしたことです。議員活動として、養護施設のような施設に行ったり、そういう方々のお話を聞きに行ったり、住宅街の本当に隅々まで歩いて直接対話をする機会を数多く持ちました。
帆刈 それまでとは違う現実が見えたのでしょうか。
ツノダ はい。日頃プロジェクトをご一緒しているナショナルブランドの大手企業のマーケティング担当者の方々は、一流企業にお勤めで、それなりの生活水準の方たちですよね。 しかしながら、大手企業の商品はどこのスーパーでもコンビニでも売っていますし、議員活動で出会ったようなごく普通の人たちも買っているわけです。
戦略的にどのような人たちをターゲットにするか、どのようなペルソナを設定するかは別問題として、少なくともごく普通の人たちの存在を「無視して」企画してはいけないと強く思うようになりました。
帆刈 それが、現在のツノダさんの視座に繋がっているのですね。
ツノダ 企業が掲げる「社会課題の解決」といった綺麗なマーケティングのストーリーには乗りにくいかもしれませんが、こういう人たちもいるよね、という事実を知った上でどのような価値を届けていくかを考える。そうした「包摂的な視点」や、うわついた綺麗ごとですまさないための「戒め」を、この経験から得たと思っていますし、近年増えている富裕層向けの企画においても価値創造の視点として意味があるように感じています。
帆刈 ツノダさんの会社のホームページを見ると「わたしたちの提供価値は『踏み出す勇気を賭けにしない』」と掲げられていますが、どういった意味でしょうか。
ツノダ これも政治の世界と通じるところがありますが、企業においても、データや生活者の声という根拠があるのに、社内事情や前例主義が最優先になってしまい、曲解された方向に進んでしまう場面というのを多く見てきました。
リサーチ結果はあくまで「過去」のもので、そこから「未来をどう読むか」が重要です。未来のことは誰にもわかりませんが、私たちの経験から「こういうことが言える」とお伝えし、未来に対する「賭けの勝率を上げていく」ことを提供したいと考えています。根拠があるのに、それを無視して賭けにしちゃダメだろう、という思いが強くあるのです。
帆刈 その背景にある問題意識は、どのようなものでしょうか。
ツノダ 突き詰めると、「もったいない」という感覚が常にあるのだと思います。せっかく御社にこれだけの資産(リソース)があるのに、それを活かせていない、伝えきれていない。新しい投資をしなくても、今あるものをちょっと組み替えたり、表現を変えたりするだけでもっと良くなるのに、それをしないのはなんてもったいないのか、と。否定するのではなく、「もっとこうすれば良くなるのに」というスタンスです。
帆刈 「ホライズン」の編集委員も長らく務められました。振り返られて、印象に残っている記事はありますか。
ツノダ 今日、実物を持ってきたんです。自分が担当して印象に残っている特集の中では、中年以降の女性を対象とした「インビジブル・マチュリエンヌ」(2019年10月)や「Z世代ホントのところ」(2022年5号)など、ある属性を見つめたものが多いのですが他の編集委員の方の記事で印象に残っているものを振り返ると「人」なのですよね、意識せずして。
例えば、中塚さんがご担当の「男性消費図鑑」(2020年4号)や、本荘さんご担当の「子どもドリブン」(2021年9号)。この「男性消費図鑑」では、まさにその人のリアルな可処分所得や、買ったものなどを見せる企画としたのですが、こういう生々しさの中に垣間見える価値観や世相が、本当に面白いなと感じます。「子どもドリブン」も、人を大事にした経営や人事が、結局、経営を伸ばしていくんだということを「子ども」を起点に丁寧に取材された上での提言となっていてとても気に入っている特集です。


帆刈 ご自身が編集委員長として、心がけていたことは何ですか。
ツノダ まずは、本当に基本的なことですが、毎月の編集会議には必ず出席する──その積み重ねを大切にしていました。
また、せっかくの限られた貴重な時間、編集委員のみなさまの視点や意見を活かせるような場づくりを心がけていました。編集委員は、みなさまオンリーワンの並外れた経験と知見をお持ちの素晴らしい方々なので。
もう一つは、紙媒体からWeb媒体へと移行の推進と、その際のコンセプト設定です。「ホライズン」の役割として「マーケティングに携わる人たちに、ゆたかなセレンディピティを。」を掲げました。いわゆるデジタルマーケティング的な手法論やノウハウ、スキルに走るのではなく、もう少し手前の発想のきっかけや企画視点として役立つものでありたい、ということです。
そのような意図もあり「ライフ」「グローバル」「ソーシャル」「アート」など、通常のマーケティングとは異なるある種「ふんわりした」フレームを設け、マーケティングを広義に捉えられるような仕掛けを決めたりはしました。
帆刈 最後に、ツノダさんにとって、「マーケティング」とは何でしょうか。
ツノダ とても大げさな言い方をすると、「恩人」であり、「私を救ってくれた存在」です。別の言葉で言うと、「自分の居場所」でもあります。
帆刈 「救われた」というのは?
ツノダ 冒頭に傍観者だったと話しましたが、私はもともと内向的で、協調性がまるでない飽き性の人間でした。間違いなく普通の企業の中では非常に生きづらかったと思います。マーケティングに出会ったことで、本当に救われました。
帆刈 その「マーケティング」という言葉の定義について、どのようにお考えですか。
ツノダ 世の中では、マーケティングというと「人心を操って売るためのもの」という、どこかあくどいイメージがまだあるかもしれません。しかし、本来マーケティングとは「人を幸せにするためのもの」だと思っています。
帆刈 人を幸せにするためのもの。
ツノダ はい。さまざまな人たちのそれぞれの幸せなくらしのために、何をどう組み合わせるべきか。その“最適解”を見つけていくことだと思っています。届ける側にとっても、受けとる側にとっても、双方にとっての最適解です。
最近では、小中学生がプロフを気にするように、セルフブランディングが当たり前になりました。マーケティングは企業だけのものではなく、もっと身近で、誰もが持つと「生きやすくなる」スキルでもあるはずです。モノやサービスを売るためだけではなく、より良いくらしや関係性を築くためにこそ、マーケティングはあるのだと思います。
帆刈 本日は、貴重なお話、どうもありがとうございました。
「どこか一歩引いて見ていると感じていた」とお聞きして、とても驚きました。自分と同じように感じていた方がここにいらっしゃった、という驚きです。自分も、どこか一歩引いてみている子どもだったと思いますし、今でもそう言われることがあります。一歩引いて見ている、が実はマーケティングの世界で強みになる、というお話を聞いて、なぜ自分がマーケティングの道に進んだのかに気づかされるとともに、マーケティングに関わるあらゆる人にとっても役立つ考え方ではないかと感じました。

ツノダ フミコ(つのだ ふみこ)
MARKETING HORIZON 編集委員長
株式会社ウエーブプラネット 代表取締役
社会動向や生活者の分析を通して、価値観変化や生活者インサイトを導き出し、コンセプト開発を行う。問いを重視したきめ細かい伴走型コンサルティングにて新しい価値づくりを支援し、企画力と気づき力を強化する研修も展開。近著『いちばんわかりやすい問題発見の授業』では、書くことで考える力を磨く「具体→抽象→発見」の手法を紹介している。

帆刈 吾郎(ほかり ごろう)
MARKETING HORIZON 編集委員
博報堂生活総合研究所 所長
1995年に博報堂入社、以来マーケティング職に従事。2013年タイ・バンコクに駐在、博報堂生活総合研究所アセアンを設立。2020年日本に帰任し現職。