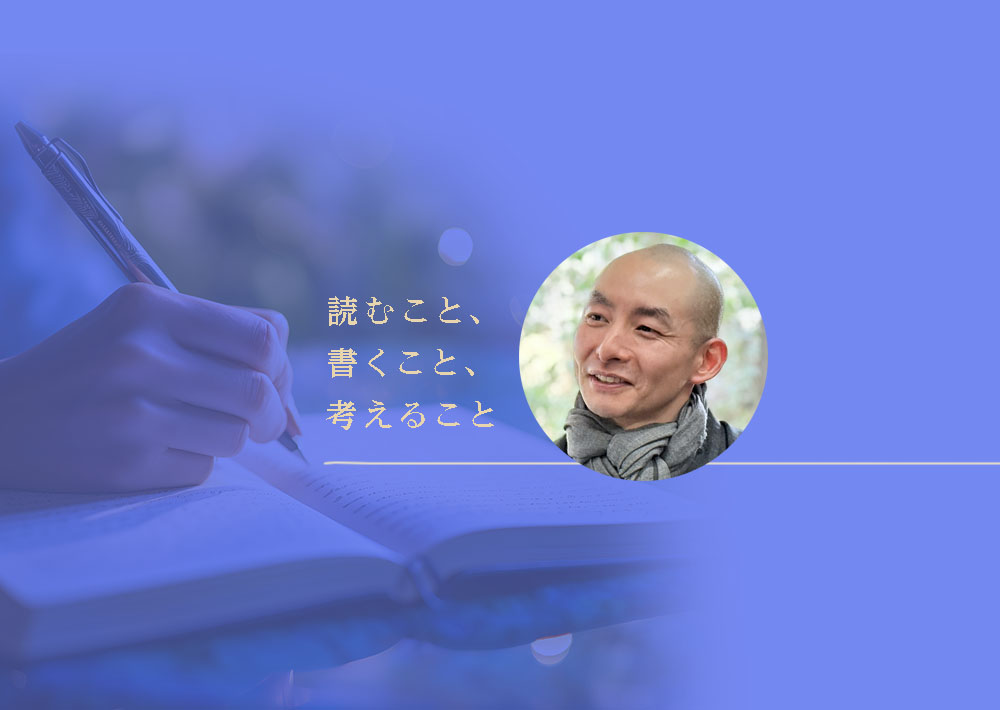井上 大光 氏
東慶寺 住職
今号のテーマである 「読むこと、書くこと、考えること」 を編集会議で検討していた際、 「写経」についてとりあげてはどうか、との案が出ました。確かに写経は最もシンプルかつ歴史ある「読む、書く、考える」の三位一体的行為とも言えます。早速、北鎌倉・東慶寺の井上大光住職を訪ねました。
東慶寺白蓮舎での写経から取材は始まった
───井上さんから取材のご快諾をいただいた際、「取材の前に(東慶寺で)写経をしてください」とのことでしたので、自宅で何度か練習をし、先ほどここで一枚書きました。
実際に写経を行う前に描いていたイメージは、般若心経の一文字一文字を書くことで無の状態に近付き、だからこそその意味が自らの中にすっと入ってくる、そういう「読む、書く、考える」が一体化した行為かなと思っておりました。
ところが、実際に自分で書いてみると、無心になる余裕など全くなく、今日で5回目の写経でしたが、回を重ねるにつれ、確かに文字は整ってきましたが、一方で書けば書くほど時間が掛かるようになっていきました。書くほどに、それぞれの文字の意味や般若心経についての関心が自ずと深まり、それらを本で調べたり、読経をBGM代わりに流したりしているうちに、単に文字を機械的に書き写す時間ではなくなってきました。考えたり味わったりしながら書くようになったため、時間を要するようになり、実は今日こちらで書いた一枚がもっとも時間がかかり、いつもの2倍近い時間となりました。
井上 ご自身のリアルな体験を通じてどう感じたのか、その体験こそが写経の価値だと思います。
自ら体験することこそが強固な礎となる
───先ほど写経場で写経をさせていただきましたが、最後に願意を書く段になり、日頃いだいている自分の中の小さな欲など取るに足らない、もはやどうでもいいことだ、と思えたことに自分自身が一番驚きました。
と言うのも、一文字一文字の意味を自分なりに咀嚼しつつ書き進めていくうちに、仏様とは言わないまでも、鳥の目で世界を俯瞰している感覚を覚えたのです。般若心経には「無」や「空」などの字も多く、また、増えることも減ることもない、生きるとか滅するとか関係ないと繰り返し登場します。書いているうちに「ならば、どうでもいいか」という気持ちになり、気持ちが楽になりました。囚われていたものが一枚一枚剥がされていくような感覚です。
先ほど写経に際していただいた説明書の中に願意の記入例がありました。 願意例の一番目に 「世界平和」とあり、以降「無病息災」「心身健康」「家内安全」…と続いていました。実は、最初見たときは「世界平和」が一番にあるなんて大袈裟過ぎる、そんなことを書くご立派な人がいるのかしら、と感じたのですが、書き終わり、願意を書く段になり、まさに自分がそのひとりになっていたのです。「世界平和」の意味をこんなに自分の中に感じたことはありません。不思議な気持ちです。
井上 それは大正解です。我々の言葉で言うと「解脱」という境地です。苦しみや囚われ、執着から解放されるのが解脱という状態ですが、写経を通じて得られる大きな功徳の一つです。
そこまで苦労して書いたら、その経験はそうそう忘れません。スマホやパソコンがこれだけ普及し、わたし自身も筆を持つ機会は減っています。一方、写経はアナログ中のアナログ、極めて非日常的な行為です。自分で墨をすり、日頃持たない筆を用いて、260を超える文字を一文字ずつ書いていく。非常に手間がかかります。日常にはこんな時間も経験もありません。まさにこの非日常性が現代における写経の大きな魅力のひとつでしょう。実際、非日常的なアトラクションを楽しむ感覚でお見えになる方も中にはいらっしゃいます。
しかし、きっかけはなんであれ、こうした体験こそが、人生にとって価値のあるものであり、最終的に自分を助けてくれるものではないでしょうか。付け焼き刃や一夜漬けではなく、面倒くさい思いをして手に入れたものや苦労して勝ち得たもの、自分の手を動かしたからこそ手に入ったものからしか得られない何かがあります。今は難なく情報を得て、気軽に自分の知識として人生を泳げてしまう時代ですが、自ら苦労して勝ち得た体験こそが自分の礎になるのではないでしょうか。写経にはそうした一面があると思います。
───写経を終えた今は、ちょっと不思議な感覚です。自宅で書いたときとはまるで違う感覚です。東慶寺さんには白蓮舎という立派な写経専用の空間がありますが、この「場」による作用も非常に大きかったと思います。室内の香りや、窓の向こう側の庭木の様子など含め、五感のすべてで写経に臨めたと感じます。写経のために、このような環境を整えられているのはどうしてでしょうか。
井上 この白蓮舎という建物は30年ほど経っていますが、実はほとんど使われていませんでした。しかし、お寺のあり方としてそれはどうなのだろうか、と思うようになりました。
コロナ禍にその問題を突き詰めて考える機会がありました。観光地である鎌倉の人流を抑制するために観光施設は閉鎖を余儀なくされることも多く、多くのお寺も追随しました。しかし本来、宗教施設とは祈りを捧げに誰もが訪れることのできる、神聖でありながらも開かれた空間であるべきなのではないか、との考えも大きくなりました。
そこで、2020年7月より拝観料を廃止いたしました。拝観料の是非ではなく、自分自身が考える宗教施設としてのあるべき姿へのこだわりです。常に開かれたお寺として存在するのであれば、写経も予約不要で毎日できるようにし、気軽に訪れていただけるようにしました。

写経による功徳、功徳を捧げる祈り
───これほど手間と時間がかかる写経ですが、そのはじまりは天武天皇の時代、673年との記録もあります。実に1300年以上続いているわけです。しかも、時短や効率化が叫ばれる現代においても、写経に訪れる人は絶えるどころか、むしろ増えているのではないでしょうか。写経の何がこの令和の時代にあってもなお人々を惹き付けているのでしょうか。
井上 基本的に写経とは祈りの行為です。さらに元をたどれば、コピー機のない時代のお仕事です。中国から仏教が伝来し、お経が書いてあるお経本が日本に入り、これをみんなに広めたいからみんなで書き写そう、と。昔はそうした仕事があり、職人さんたちがいました。それが平安時代になり、貴族の人たちややんごとない方々がお経を書き写して、お寺に奉納してご祈願をするという祈りに変わりました。時代ごとの変化はありますが、共通しているのは祈りです。何の祈りであれ、そういう気持ちでお写経をし、観音様にお供えするのがやはり良いのではないでしょうか。健康第一、必勝祈願、合格祈願など、現代でも基本は祈願ですよね。アトラクション感覚であったとしても、まずは写経に触れることが大切なのです。
お経は読んだ人、書いた人に功徳(神社で言えばご利益)が積まれます。一生懸命読んだり書いたりすることで、その人に備わった功徳を観音様や仏様にお供えし、「わたくしが積んだ功徳をお供えしますので、どうかほんの少しだけでもわたくしの願い事にも耳を傾けていただけませんか」という順序になるわけです。ですから、写経をしたのであれば、まずは奉納をお勧めしています。写経用紙を記念に持ち帰る方もいらっしゃいますが、せっかくの功徳をお供えして願われた方が良いのではないでしょうか。
祈りを捧げるということまでがお寺における写経の意味であり、東慶寺における白蓮舎の存在意義です。
そぎ落とすからこそ、本質が残る
───ところで、拝観料を廃止したことは非常に重い決断だったのではないでしょうか。写経のための会場をはじめ、東慶寺の施設維持や庭園管理には人手も要します。何が井上さんをそこまでさせているのでしょうか。
井上 決断をし、実行に移してからしばらくは本当に大変でした。しかし、先ほど申し上げたような自分なりのお寺のあり方は譲れませんでした。誰にでも開かれた神聖な場所であること、そこにこだわり続けていくことで、やがてお寺自らがそうなっていきます。ですからでそのこだわりを発信し続けてもいます。
こうしたことにより、どのような時代になっても必要とされる寺になると考えます。わたしが住職をしている期間なんて、長くてあと30年ぐらいでしょう。いつかは誰かにこのお寺を引き継がなきゃいけないわけです。神聖な場所としてみんなに必要とされているお寺、お花がきれいに咲く時期だけ観光客が来るのではなくて、信心深い人が足繁くお参りされるお寺にしておけば、時代が変わってもずっとそういう佇まいや意思が脈々と受け継がれていき、再びコロナみたいな時代が来ても乗り越えていけるはずです。これまでも人々に必要とされ、意味や価値があるからこそ、こうして受け継がれてきたのでしょう。これほど進化したデジタルの時代であっても、不思議なことにそれだけで十分だとはなりません。スマホやAIと墨や筆が共存していく。やはり表があれば裏があるように、そこには何かしらの意味、価値があるのでしょう。
───これから先の千年、この東慶寺をどのように維持し、次代へとつなげていくお考えでしょうか。
井上 東慶寺には700年の歴史があります。その間、順調な時代の住職もいれば、困難に直面した住職もいました。その時々の住職が次の世代のために懸命に努め、それを繰り返して今に至ります。
以前、裏千家のお家元が非常に印象的なことをおっしゃっていました。「我々お茶の世界の家元というのは、野球の中継ぎピッチャーみたいなもの」だと。千利休が先発ピッチャーで、あとは全員中継ぎピッチャー。中継ぎにもさまざまな役割がありますが、お茶の世界でいえば、栄華を極めるいい時代に家元になる人もいれば、立て直しが必要な時代に家元になる人もいる。それぞれその時々の役割と責任がありますが、マウンドに上がった以上は全力で投げ切らなければなりません。
東慶寺においても、次の住職、そしてその次の住職たちに「あのとき井上住職がこれをやっておいてくれたおかげで助かった」と思われることを、できるだけ多く残したいと考えています。逆に、余計なことをしてくれた、と思われることは避けるべきです。時代によって何が正しいのか、それは変わっていく部分もあります。しかし、後の世に受け継いだ人にとってマイナスになるようなものは残してはなりません。どの業界でも同様でしょうが、「やらなくていいことはやらないほうがいい」というのが鉄則です。
拝観料を廃止したことで経済的には確かに苦しくなりました。しかし、新たな道が拓けたりもするものです。ギリギリの状態だからこそ、さまざまな工夫を凝らすことができます。特に臨済宗はその傾向が強いのではないでしょうか。
不要なものをどんどんそぎ落として、本質に迫る。お寺の建築も極めて簡素です。可能な限り無駄を省き、必要最低限の形で本質に向き合い、突き詰めていく。自立しているお寺として次の代へ渡していく。わたしにできるのはそれだけです。
───本日は目が覚めるような写経体験だけでなく、お寺のあり方に至るまで写経を通じて世界が広がりました。貴重なお時間とお話、ありがとうございました。
インタビュー後記
インタビューは観光客もまばらなしんしんとした寒さの一月下旬の平日、本文中にも登場する東慶寺・白蓮舎で行われた。芽吹きを待つ色のない庭木の中、春の訪れを告げる蝋梅の黄色が磨き上げられたガラス越しに見えていた。
インタビュー前の写経。無駄なものは何もなく、静謐な美しさに満ちた空間で墨をすり、一文字書くごとに呼吸と姿勢を整えた。そういう動きが自ずと促される空間であり、時間だった。
井上住職は「お寺としてのあるべき姿」をとことん追究し、その実現に日々取り組まれている人だった。企業経営に置き換えるならば、まさにパーパス経営。業界の常識や成功体験に甘んじることを是としない覚悟がひしひしと伝わった。そのことの具体を語る言葉は少なくとも、身を切る覚悟で臨むとはこういうことを指すのだろうと、その潔さと信念は強く響いた。
次の代、さらにその次の代、そしてそのずっと先。その時々の正解は違えど、存在し続けるために必要な意義の核心を得た井上住職にブレはない。主(あるじ)のそうした信念が白蓮舎の空気を作り、書くことによる内観の特別な時間を生んでいる。
蛇足なのは重々承知のうえで付け加えると、これこそマーケティングのあるべき姿だ。
(Interviewer:ツノダ フミコ 本誌編集委員長)

井上 大光(いのうえ だいこう)氏
東慶寺 住職
昭和58年、前住職 井上正道の二男として生まれる。
大学卒業後、円覚寺専門道場 横田南嶺老師の元で修行。
平成25年より住職に就く。