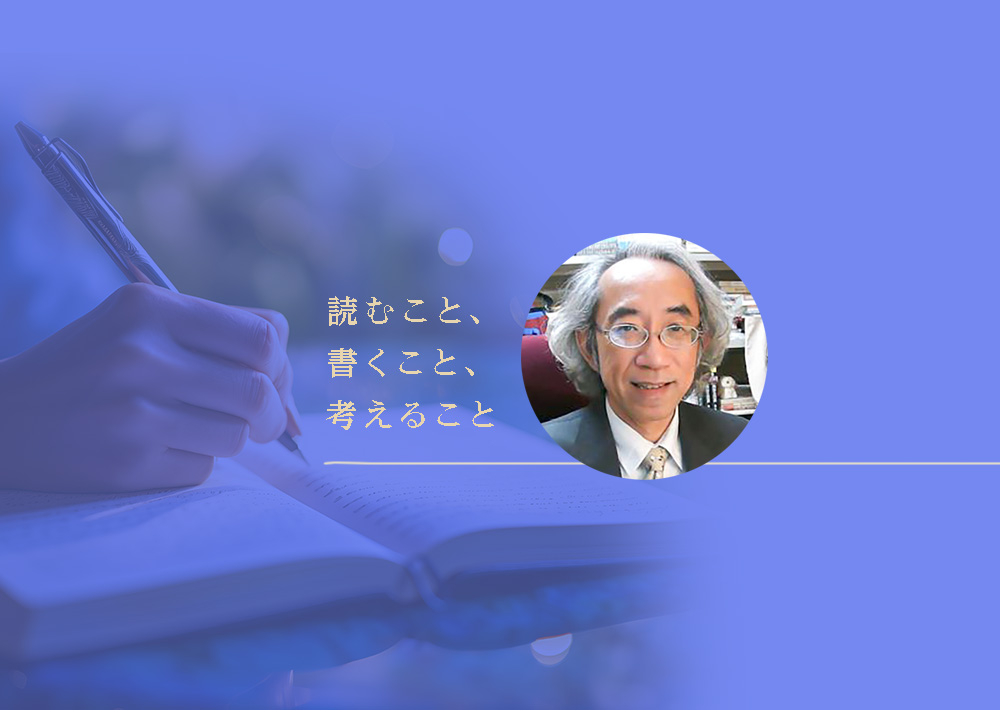森川 亮 氏
近畿大学 経営学部 教養・基礎教育部門 准教授
1:「思考」に関連して、はじめに憎まれ口を・・・
ここのところ産業界から聞こえてくることは、若者の元気のなさを嘆く声である。2000年代に入ったあたりからずっと言われ続けてきたことであるが、昨今は、さらに深刻度を増しているようだ。若者が思考しなくなった、面白味に欠ける、というのである。平均的には優秀だけれど、とにかく面白味がなくて思考が画一的らしいのだ。もう、このままではあらゆるものが枯渇してしまうとの危機感が広がり始めているとのこと。
しかし、考えてみて欲しいのである。画一化された労働者を望んだのは、他ならぬ産業界ではなかったのか。命じられたことを忠実に、そして確実に遂行できる「即戦力」ではなかったのか、ということである1。大学は(高校、中学なども)、役に立たないことを教えるのではなく、もっと役に立つことを教えろ、ということをさんざん要請してきたのは、産業界であった。もしくは、そういう世間的な空気をさんざん醸成してきたのは、間違いなく産業界であった。特に経済的な失速が誰の眼にも明らかになってきた2000年以降、こうした雰囲気は極めて強固なものになった。
若者は、世間の雰囲気に敏感である。 彼らは産まれて此の方、 世の雰囲気に合致させるように自らを即戦力として可能な限り最適化したにすぎない。 余計なことをせず、 役に立つスキルを身に付け続けた結果が昨今の若者を、 延いては昨今の日本の多くの労働者を創り上げたのである2。要するに、昨今の若者の姿は(そして多くの労働者の姿は)、社会の、つまりは産業界の求めた型に応じた姿だということである。
1 こんなのは、本当はロボットである。しかし、そこまで考えずに「即戦力」と言ったのではないか? で、ロボットにどうして「考えろ」などと言うのか? それともAIに置き換えるというのか・・・。それにしても、AIに置き換えてすべてアウトソーシングしたらすべてがスカスカになるだろう。
2 ただし、「役に立つ」と言われていることを身に付けても本当に役に立つとは限らない。むしろ役になど立たないであろう。というのも、こうした大方の「役に立つ系」の諸々は、「How toモノ」、あるいは結局のところそうした類いの知識に分類されるようなモノにすぎない場合がほとんどだからである。
いや、ここは批判を覚悟の上で、もっと単刀直入にあえてキツイ言葉でハッキリと申し上げよう。型に嵌まった労働者を求めたのは他ならぬアンタだ、ということだ。それを棚に上げて昨今の状況を深刻に憂いているというのであれば、まったくもって笑止千万! 度を超して滅茶苦茶である。他ならぬアンタも思考停止しているとしか言いようがない。「最近の若者は思考力が無くて・・・」などと嘆く前に自らの頓珍漢さをしっかりと自覚することが先だろう。ビジネスの外部からアンタ方の話を聞いているに、ほとんど皆が、同じような言葉で同じような内容をいかにも自らが熟考したかのように宣っているではないか。そんなものは、安っぽいビジネス書の類いにそれっぽく書かれている安易な言葉を得意げにオウム返しにしているにすぎない。要するに、アンタの思考も若者と同程度に薄っぺらな、借り物の、浮いた言葉の羅列でしかない。少なくとも私にはそう聞こえる。とにかく、まずはそうした自身の姿を自覚すること。道義として、話はそれからというものだ。
なお、予め言っておくけれど、じゃあ、思考力を涵養する教育にシフトしよう、などと言い出してもダメである。あまりにも無茶苦茶で支離滅裂の思考停止状態なので、アンタ方は、またしてもそんなことを言い出しかねない。だから予め言っておくのだが、それはそれで、「そういう型」に嵌め込むだけのことである。思考力なるものは、ちょっとした小手先の変化で涵養できるようなものではない。そもそも思考力を付けることなど意図してできるものではないのだ。むしろ、意図することを放棄しなければ創造性も個性も、延いては思考力なるものも、育ち得ないのである。
「型」という語をさんざん述べてきた。なかなか短く述べることは難しいのだが、これについても簡潔に述べておこう。端的に述べると、近年の若者は、どうでもいい型に雁字搦めにされて重要な型を教え込まれていないのである。プレゼンの仕方や企業経営に纏わる様々な用語の数々など、挙げてゆけばキリがないのだが、こんなものは後から何とでもなる、上部構造のそのまた上部構造に属する型ではなかったのか、ということである。基本的な下部構造たる型は、「読み書き算盤」である。今も昔もこれは変わっていない。即戦力ということで、こうした基本的でもっとも重要な型の習得を緩めてしまい、枝葉末節の型を重視することになってしまったのではないか、ということである。基本の型である「読み書き算盤」がしっかりと構築されていれば、その上に個別の型を構築することは比較的簡単なことである。そして、臨機応変に構築した型を無化してみることも、つまりは型を破ってみせることも難しいことではなかろう。
われわれは、ここらで蔑ろにしてきた基本に立ち返らなければならない、ということではないだろうか。本題に入る前に、こんな苦言を申し上げておく次第である。
2:思考と身体
さて、上記も迂遠に思考全般に関わるのではあるが、ここからが本題である。
人間はいかにして思考するのか、考えるのか、ということについてである。
じつは、この問いに対して最終的な答えが確定しているわけではない。分からないことだらけ、というのが本当のところである。色々と論じられ語られてはいるが、いずれも結局のところ仮説にすぎず、本当のことは分からない。なんとなれば、この問いは、「私とは何か?」という問いを避けることができないからである。そして、すぐに了解されることであろうが、これらについて考えを巡らすということは、そもそも自己言及的であり、単純に言うと「考えることを考える」ということになっているのである3。したがって、ここでは、経験的に「人間の思考」の根幹に関わると推察される基本的なことを概説し、現代の諸問題の根幹を考察する一助としてみたい。
3 ということは、物理学に代表される精密科学も世界を理解することは原理的に極めて困難だ、ということである。世界を理解するには、世界の一部たる理解する側の私を理解しなければならず、結局は、ここで述べている問いの前に立たざるを得ないからである。
2−1:フォークボールを投げる
唐突だが、フォークボールの投げ方をご存じだろうか? よっぽどの野球オンチでなければフォークボールは人差し指と中指でボールを挟んで投げるという、 ボールの握り方は、 野球に纏わるちょっとした豆知識としてご存じのことだろう。 では、その知識でもってフォークボールを投げてみよ、 と言われたらどうか? 野球経験者ならいざ知らず、 ほとんどの人は投げられない4。やってみると分かるが、ボールはすっぽ抜けてしまい、前にすら飛んでいかないことだろう。しかし、何度かボールを挟んで投げる練習をするうちに、やがてボールは少なくとも前に飛んでいくようになる(けれど、まだ落ちない!)。で、何度も諦めずに、根気よく、試行錯誤を繰り返しながら投げるうちにボールをちょっとお辞儀させるくらいに落とす、ということが可能になってくる。もちろん、この道のりは結構ハードである。だが、原理的には、ボールをそれなりのスピード5で真っ直ぐに投げることができるだけの体力があれば、確かに挟んで投げればボールをストレートラインから下方へ落とすことくらいはできるはずである。繰り返すが結構ハードではあるが・・・。
このちょっとした思考実験(思考訓練?)は非常に示唆的である。まず、ボールの握り方を知っている(投げ方というよりも)というレベルの知識と、実際にフォークボールを投げることができる知識では知的深度がまったく異なる、ということである。後者の方が知識として圧倒的に深いことは言うまでもない。後者の知識は確実に血肉化されており、身体化していると言える。そして、後者の理解が得られれば、そこから付随的に様々なことが身体的な実感を伴って、この場合なら指先の身体的な感覚を付随させて想像可能となる。ひとつでもこういう感覚を身に付けると、実際には自分が投げられない球種についても圧倒的に理解が深まる。どんな状態でボールを握り、どのように投げれば、そして、どのくらいのポイントでボールをリリースするか、どんな具合に指に引っかけるか、などなどでボールの軌道が変化するということが、身体を通した経験として想像できるようになる。と同時にプロの投手が投げる変化球がとてつもないレベルだということも実感を伴って想像できるというものである。
4 ここでカーブじゃなくてフォークボールというのがミソである。カーブ程度ならボールを切って投げれば(つまり回転させて投げれば)、初めての一投で山なりの放物線のスローボールであっても軌道が曲がるくらいはするからである。実際にやってみると、思ったほど難しくはなくて、簡単にボールの軌道は曲がってくれる。
5 少なくとも100km/h弱くらいの球速は必要だろう。
おおよそ、物事を考える、熟考する、とは上記のようなことである。「ボールを人差し指と中指で挟んで投げる」という知識はただのマニュアルにすぎない。これだけの知識だけでは、付随する何かを求められてもこれ以上のものはでてこない。とっても薄っぺらなのだ。で、ここが重要なのだが、どの教科書でも、あるいはいかに優れた指導者であっても結局のところ、いかにどう言おうが、いかにどうやってお手本を見せてみようが、教えられることは、どこまでもマニュアル程度のことまで、なのである。いくら「もっと腰を入れろ」とか「もっと腕をしっかり振れ」とか「リリースの時にスナップを効かせろ」とか、いかに言葉を尽くして、それどころか実際にやって見せてみても、それはそういうマニュアルに留まるのである。当の本人が、実際に身体を動かしてその感覚をつかみ取り、自らの身体的な了解が得られなければ知識は深まらないし定着もしない。つまり、思考の歯車は本当には動き始めないのである。
2-2:身体が思考を紡ぎ出す
もう一つ例を挙げよう。
たいていの数学者、物理学者の研究室には黒板がある。あるいはホワイトボードなどがある。もちろん、これ以外の専門家の研究室にも黒板やホワイトボードがある場合が多い。物理学から哲学へと足を突っ込んでしまい、文理両生類のごとくなってしまった私の研究室にもある。なぜならば、とにかく、思いついたり気になったりしたらすぐに数式を書いて弄くり回したいからである。つまり、黒板に数式を書いて考えたいのである。言い換えれば、手で数式を書き下すことで考えることができるからである。もっとも、黒板やホワイトボードである必要はないし、なければ紙の上に数式を書き殴るのだが、ベストは黒板やホワイトボードであろう。理由は後々ゆっくりと説明しよう。
ここで、注意を促したいこと、そして強調すべきことは、数式を書き(とにかく、黒板だろうが、ホワイトボードだろうが、紙だろうが)、それを弄くり回すことで思考が深まるということである。あるいは思考する、ということである。教科書や論文に書かれている数式について、その論旨に従って自分の手で実際に変形してゆくのである。「(1)式に○○の条件を入れると(2)式となる」というのであれば実際にやってみるのである。ここで、腕組みをしたまま「ああそうか」とか「ふーん」とか、論理の筋が分かったからといってそのままにはしないのである。実際に計算(式変形)してみると、「なるほど!」となって身体がまさしく了解するのである。この身体的了解は、非常に重要である。手を動かして了解することで、知識が血肉化する。つまり、身体化するのである。
こうした血肉化した知は、思わぬ箇所で、時には本人すら意識することなく、異なった文脈、異なった数式に対しても威力を発揮することとなる。どういうことか? 数式という記号・言語に慣れてくると、書き下した数式の形が勝手に次の数式を準備するがごとくに、あるいは、自動的に手が次の数式を書き下すかのごとくに、自ずと思考のプロセスを進めてくれることがある。手が勝手に身体化された知を総動員するように数式を弄り始めるのである。一連のプロセスが、困難な箇所に直面して止まってしまっても、ゴチャゴチャと数式を書いて弄くり回しているうちに次の展開を書かれた数式と手が協働するように導き出してくれることがあるのである。
はたして考えているのは、頭なのか手なのか? これについては、頭だと思われる場合もあれば、手が自ずと何かを引っ張り出した、と言いたくなる場合もある、というのが正直なところである。ただし、ここでちょっと言及しておきたいことは、頭脳も結局は身体の一部である、ということである。
さて、数式について述べてみたが、こうしたことは、じつは、数式に限られた話ではない。数式のような抽象的な言語の場合により特徴的であるのは事実であるが、こうしたことは、自然言語6による言語活動の中にも見いだせるものである。ペンを取って紙の上につらつらと文章を書いてみるとよい。抽象的な文章であっても、感情的な文章であっても、おおよそ文章なるものを書き始めて集中度が高まり、文章と自分が一体化してくると、書いた文章が次の文面を準備してくれるような感覚を覚えることはよくあることであろう。手と書かれた文章が自ずと次の展開を準備するかのような、つまり、よくよく後になって客観視してみるに、頭が考えたのか、手が考えたのか、はたまたそれまでに書いた文章が考えたのか、何とも言い得ない状態を経験することはよくあることのように思われる。心と身体と文章の渾然一体化した何かが思考を紡いだとしか表現しようのない状態である。
6 自然言語とは日本語や英語のような、われわれが日常的に用いる言葉のことを指す。これに対して数学は形式言語で人工言語に分類される。その他の人工言語の典型例はC言語、プログラミング言語、などである。
近代の合理的な科学は、それまでに書いた文章を読み、頭が(頭脳が)次の展開を論理的に取捨選択し、それを手に伝えたのだ、と説明することだろう。しかし、本当は、すべてが渾然一体化して協働するのではないか? 次の文章が湧き出るように、何やら自ずと出てくるような場合には特にそうした感を強くする。ここに、近代合理主義的な因果論を持ち込んでも思考が紡ぎ出される本質にも瞬間にも迫れないのではないか、と私は穿っているのである。手が文字を書き、それを眺め、頭脳が作動し、あるいは手がまた何かを書き下す。このグルグルと回る循環と渾然一体化した相互関係・相互作用そのものが思考することであり、それ自体が思考を紡ぐのである。このように断言することは避けるべきかもしれない(思考とはそもそも謎なのであるから!)。しかし、確かなことは、頭と手とテクストは、数多の哲学者が言及してきたようなある種の解釈学的循環7の構造、そして関係性を有するということだ。
そこで、黒板やホワイトボードの利点についてである。今、手が書き、それを眺め、と述べた。黒板やホワイトボードの場合は、眺める視点を物理的に変えることができるのである。机の上の紙の場合は、退いて眺めるにも限界がある。立って黒板やホワイトボードに書いてみれば、ぐっと退いて眺めることも、立ち位置を変えて斜めから眺めてみることも簡単なことである。実際に、「あれ?」となって一連のプロセスが止まってしまった場合や、何か根本的に重要な箇所に差し掛かっているように思われる場合などには、「う~ん」と唸りながら、立ち位置を変えて退いて全体をぼんやりと眺めてみたり、分かりきった数式展開を余白であえて行ってみたり、気になる箇所をグルグルと丸で囲ってみたり、文字通り数式の周りを右往左往する場合が多い。この時、われわれ人間の内部で何が生じていて、究極的かつ根本的に何をしているのか、それは本当には分からない。これは、最初に述べたように謎である。しかし、このようにして思考は深められ、新たな展開を見出す、あるいは見出そうとするのである。
7 解釈学的循環とは、要するには、「全体の理解は部分の理解に依存するのみならず、部分の理解もまた全体の理解に依存するような状態(ディルタイ)」にあることを指す哲学用語・概念である。かかる循環をハイデガーは、時間性と見做し、先行解釈と新たな解釈の関係性として捉えた。
本論で強調したいことは、手が新たな何物かを記し、それを視認して頭脳が作動し、そしてまた手が何かを記し、そしてそれを視認して頭脳が作動し・・・・・・(手が何かを書き加えたことによって全体が変化し、そしてその全体を見て解釈が若干ながら変化し、解釈が変化したことでまた手が何かを書き加えることとなり、それによってまた全体が変わり・・・・・・、といった循環が生じるということである)、という一連の過程もまた、かかる解釈学的循環の構造とパラレルだということである。つまり、思考とは、解釈に次ぐ解釈を身体と頭脳がこのように協働し、あたかも無限ループであるがごとく続く過程であると言えよう。
さらなる詳細は、参考文献、その他に提示する[4]と[5]に詳しい。
2−3:世界と私の出現
思考と身体の協働性、より正確には意識と身体との協働によって思考することについて述べてきたが、この協働性の源はどこにあるのであろうか? 結論から述べておくと、これは私の出現の瞬間にまで遡ることができる。そして、それは同時に世界の出現でもある。
これらは、おおよそ以下のような機構で生じる(とされている)。
生まれたての赤ん坊は、まったくの自他未分離の状態にある。自分と自分以外の区別も付いてはいない。この状態から人は(赤ん坊は)、他者を模倣することで自他を分離するに至るのである。ちなみに、この模倣というシステムは本能的に赤ん坊に(すべての人間に)インプットされているとされる。つまり、赤ん坊は、周りの人から微笑みかけられ、それを模倣して微笑み返すという自動運動を繰り返しつつ、一方では生物学的に急速に成長し、自らが微笑み返しているという身体動作を自覚するのである。もちろん「微笑み返している」という高度な言語的な認識ではない。あくまでも自動運動として、自動的に微笑み返す際に自身の身体が動いていることの自覚を得るのである。つまり、自らの身体を自覚する。これが言ってみれば「私の出現」8である。と同時に客観世界(自分以外)の出現でもある9 。
この過程は何度も複数回にわたって、それこそ数え切れないほど繰り返される。母親から、父親から、そして周りの人々との間において。そうした中で強化された自他の境界線は、より明瞭になってゆく。そして、この微笑みかけの過程の中で「あー」「ばー」といった声かけ、すなわち音声が、やがて「わたし」という言葉へと結実してゆくのである。もっとも、この段階まで至ったのであれば、赤ん坊の内面はかなり高度に複雑化していて複数の対象に対して言語的な認識がなされている。と同時に対象世界たる外界もどんどんと高度に複雑化してゆくのである。
それにしても、この過程はいかにも示唆的である。われわれの最初の気付きは、他ならぬわれわれの身体なのであり、この自覚的対象化が最初の思考であるというのであるから。すなわち、結局のところ、すべての思考は、いかにそれが高度に抽象化しようとも、かような過程で生じた身体というリアリティと原理的に結びついているのである。言い換えれば、いかなる思考もこの基盤たる身体から遊離してはありえない、ということである。
かくして、思考は身体性を伴うということ。あるいは、身体が思考を紡ぐということである。ただし、これもまた、経験的にこのような説明が可能ではないか、というだけのことであり、より根本的に(という言い方をするといささか還元主義的なのではあるが)は謎めいているのが思考であり、私であり、そして人間である。やはり、このことを、ここで改めて確認しておくこととする。
8 これはラカンの「鏡像段階」より前の段階である。鏡像段階についての詳細は、ジャック・ラカン著「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」、『エクリ Ⅰ 』、弘文堂(1972年)pp.123~138.を参照のこと。
9 自分の身体を自覚したのであれば、それ以外は客観世界である。まずは、このように主客の分離がなされる。
3:薄れゆくリアリティ、希薄化する人間
上記したことで強調したいことは、要するに思考とはとてもリアルなものである、ということだ。身体にリアリティを感じない人はいないだろう10 。思考とは、われわれの意識が身体と協働し、両者がシンクロして創発するものであるし、身体と協働するのであってみれば、世界と共振することで紡がれるものなのである。
ところが、近年、この協働とシンクロが切れ始めている。PCやスマホ、ありとあらゆるデジタル機器は、間違いなくこうした繋がりを希薄化し、やがては切ってしまう力として作用する。いくらキーボードを打ち、指先を動かし、もしくはペンタブで文字を書いたとしても、紙の上に書き、紙の本をめくり、チョークと黒板が擦れるリアルな質感からはほど遠い。その結果、言葉がリアリティを喪失してゆき、身体性を伴うことなく言葉だけ単独で虚空に浮遊するような事態となる。その当然の結果として、思考は薄っぺらなものとなり、思考する私の輪郭すらもが薄れてゆくという結果をもたらす。
手書きで文章を作成した経験が豊富にある世代だと実感があるだろうが、手書きの文章とPCで作成する文章では、微妙に紡ぎ出される思考が異なっているように思われたものである。ペンを取り、原稿用紙の上に文字を書く場合にはあったザラザラ感や紙とペンの質感や、そういった諸々が一気に捨象されてモニターの表面に映し出される綺麗な、しかし冷たい活字に取って代わったことで、われわれの思考はおそらくは変わったのである。ここで、「おそらくは」と記したのは、これを実証する研究はないということと、実証するのも困難であろう、ということからである。しかし、道具と思考は相互にお互いを規定する関係にある。キーボードとモニターが紡ぐ思考と紙とペンが紡ぐ思考は自ずと異なってくる。
かくして、思考はわれわれの身体から離れて徐々にリアリティを無くしてゆく。リアリティを無くしてゆくという実感もないままに無くしてゆくであろう。少なくとも文明はそうした方向へと進んでいるように思われる。つまり、思考することが人間の人間たる所以であるのであってみれば、人間は人間であることを徐々に放棄しようとしているかのごとくである。そうであれば、われわれは、絶体絶命の危機的事態に直面していることになる。
この事態に対抗する唯一の方法は、思考にリアリティを与えることである。それには、言葉にリアリティを与えなければならない。これを意識的に行わなければならない。新しい言葉、新しい概念に出会ったら、それを自らの血肉化された言葉の数々で説明・解釈することを試みなければならないのである。これでもか、これでもか、と意識的に対象を言葉の網の目に絡め取るように説明して解釈し尽くそうと試みなければならないのである。そして、既存の世界の中にその対象を立脚させることを試みなければならない。そういう徹底した解釈に次ぐ解釈の積み重ねによってひとつの概念が思考として身体という足場を得ることができる。つまり、リアリティを獲得することができるようになる。だが、こうしたことも、近年ほとんど行われなくなってしまっているように見受けられる。
しかしながら、これはもはや致し方ないのかもしれない。というのも、AIの出来損ないであるかのような人間観が喧伝され、結局のところ、人間も(人間の思考も)コンピュータのような情報の処理作業を行うものにすぎない、というのであれば、やがて本当に人間はその程度のものへと成り下がることとなるからである。少なくとも近代合理主義の説くところはそういった人間観である。われわれが思い描く世界観は、やがて世界をその通りのものへと変貌させることとなる。
近代はヨーロッパの所産である。この近代は、人間を歴史上あり得ないほど豊かにし、われわれをあり得ないほどの文明の高みへと至らせた。そしてまた、われわれは、さらなる高みへと至ろうとしている。あたかも上昇を続けるバベルの巨塔のごとく。寓話のごとく、われわれの文明は、自らの極北において、われわれ自身を自らの文明でもってして、いみじくも俊英なる政治哲学者レオ・シュトラウスが述べた通りに未完のまま終焉させることとなるのであろうか・・・?11
われわれ自身はどうありたいのか? あるいはまた、われわれは何者であるのか? われわれは、かかる問いを問い続けなければならない。なぜならば、かかる問いを問い続けることこそが、われわれを人間であり続けさせる唯一の源なのであるから。
10 言い換えれば、このリアリティのあり方が思考を左右すると言える。精神的な変容(要するには精神病の類い)による思考の変容や混乱が、時として身体性の変容感を伴うのは、こうした理由からであろうと推測できる。
11 レオ・シュトラウスは、1963年の「現代の危機」という表題のデトロイト大学での講演の中で、近代というプロジェクトに根本的な懐疑を述べている。つまり、端的には失敗した、と述べているのである。
参考文献、その他
[1] 森川亮、『思考を哲学する』、ミネルヴァ書房(2022年)
[2] 酒井邦嘉、『デジタル脳クライシス——AI時代をどう生きるか』、朝日新書(2024年)
[3] 佐伯啓思、『現代の虚妄 現代文明論序説』、東洋経済新報社(2020年)
[4] ハイデガー、『存在と時間1~4』、岩波文庫(2013年)
[5] ディルタイ、『精神科学序説 上・下』、以文社(1979年、1981年)
『ディルタイ全集 第1巻、第2巻』、法政大学出版局(2006年、2003年)
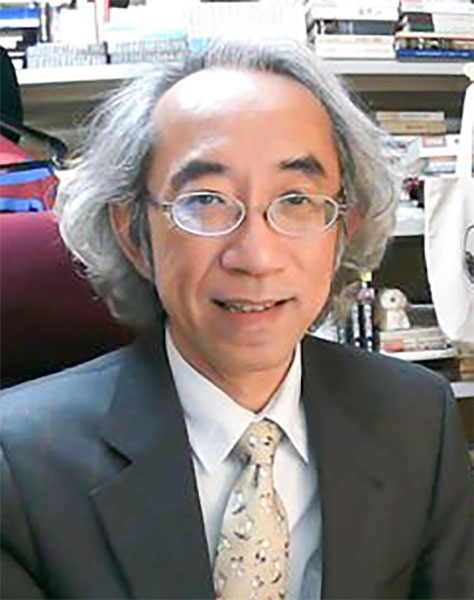
森川 亮(もりかわ りょう)氏
近畿大学 経営学部 教養・基礎教育部門 准教授
1969年岐阜市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。Birkbeck College, University of LondonにてBohm-Hiley理論の研究に従事する。神奈川大学非常勤講師、山形大学准教授を経て現職。専門は物理学の哲学・思想、及び現代思想。
主な著作に、 『思考を哲学する』、 ミネルヴァ書房(2022年)、 『社会科学系のための鷹揚数学入門—微分積分篇—[改訂版]』、学術図書出版社(2023年)、『社会科学系のための鷹揚数学入門—線形代数篇—[改訂版]』、学術図書出版社(2024年)、“The Bohm Approach to Quantum Teleportation and the Implicate Order” IRPHY 3(2). 2009。ーーいずれも単著。