福田 淳子 氏
昭和女子大学大学院 生活機構研究科・人間社会学部現代教養学科 教授
はじめに
「読む」行為は、いわずもがな、目で認識された活字が脳に伝達されることで考える行為に繋がる。刻まれた文字の記憶が蓄積されて語彙力を高め、さらに思考力を高めることになる。「書く」行為も同様、手を動かして書かれた文字を認知する作業によって思考が働き、記憶されていく。「読む」「書く」行為はまさに「考える」行為に直結している。
しかし、デジタル化が進む現代、何で読むのか、何で書くのか、何でどのように考えるのか、複数の選択肢が生まれた。昭和生まれの人間としては、紙の新聞や雑誌を読み、鉛筆やペンで書くことを前提として「考える」行為の大切さを主張したいところだが、学校教育にはデジタルの教科書や教材が導入され、特にコロナ禍においては重宝されて普及し、生徒や学生はデジタル端末とデジタルペンを使って授業を受けることが当たり前になりつつある※。かくいう筆者もまた、パソコンのキーをたたいて文字を入力し、スライドに入力したデータをプロジェクターで投影して講義を進め、クラウドを用いて学生に資料を提供している。それでもやはり、紙の書籍や新聞を読むこと、手を動かして文字を書くことの大切さを学生には伝え、デジタルとうまく共存する道を探ってほしいと考えている。
変化と維持
筆者が所属する昭和女子大学人間社会学部現代教養学科は、2003年に開設された。社会科学分野を中心とした学際的な学びで教養を身につけ,複雑化する現代社会の諸問題を的確に捉える判断力を磨き,社会の変化に柔軟に対応しながら社会と積極的に関わることのできる学生を育てることを目標に掲げてきた。つまり、現代社会に常に向き合う学科という意味では、教育方針はもちろんのこと、内容そのものも必然的に時代に合わせて進化し続けなければならない学科であり、学生とともに学科そのものも成長し続けてきたと言える。20年以上の歳月の中で、「現代教養学科(Department of Contemporary Liberal Arts)」という学科名を変更すべきではないかという判断を迫られたことも何度かあったが、所属教員たちが死守してきた。変化して「進化」する一方で、変わらない良さを維持して「深化」してきた学科でもある。
社会科学分野を中心とした幅広い学びを、「社会構想」「メディア創造」「多文化共創」の3つの領域に分類し、「地域をみる目」「文化をみる目」「メディアをみる目」など6科目の「みる目シリーズ」と呼ぶ1年次必修授業で学問の基礎的視野を広げ、2年次以上で専門的知識を段階的に深めて行く。同時に,学んだことを社会で運用する実践的な知に近づけ,発信力や分析力を高めるために,日本語や情報,社会調査関連科目などによって「スキルやリテラシー」能力を磨く。さらに地域社会や企業と連携したプロジェクト活動などの「実践」を通して現代社会の課題を見定め,企画立案やイベント運営などを経験することによって課題を解決するための学びを深めている。
「学び」と「スキル」の両輪は学科開設当初から変わることなく、学びを運用するための日本語、英語、情報のスキル科目は学科の特色として維持し続けている。日本語表現の授業は各大学において当たり前のように取り入れられているが、その方法や様態は様々である。大学での授業では、高校までの文章表現とは異なるスキルが求められるため、論理的思考や論理的表現を鍛えるためのアカデミック・スキルズやスタディ・スキルズとして、日本語表現を初年次教育に取り入れている大学も多い。しかし、当学科ではそれ以上に、単なる言語としての日本語ではなく、教養を運用するための学びに直結する力として位置づけている。創設当時から在籍し、変化と維持の両面からその姿を見届けてきた筆者が担当してきた「日本語表現」の授業を中心に、「考える」授業の取り組み例として紹介したい。
日本語スキル科目の工夫
日本文学研究を専門とする筆者は、学科においては文化関連科目を担当し、日本語スキル科目のコーディネーターを務めながら授業も担当してきた。日本語表現を「書き方」と「話し方」に分け、基礎的内容を1年次の必修科目とし、筆者は「書き方」を担当、「話し方」はアナウンサー経験のある非常勤教員が担当、20名前後の少人数授業として実施してきた。
当初は1年間の通年科目であったため、論理的な文章の書き方に重点を置きながら、手紙や履歴書(エントリーシート)の書き方等の実践的な内容も含んだシラバスを作成した。やがて大学のカリキュラム方針がセメスター制(1科目半期15回)に変更されると、日本語スキル科目の編成を大幅に見直し、「書き方」は「基礎」「実践」「応用」として段階的に積み上げる学びを構築し、「話し方」は「基礎」「ナレーション」「プレゼンテーション」として多様な表現力を身につけることを目指して今日に至っている。
「書き方/基礎」は、文字通り大学での学びの基礎となる表現力をつける内容、つまり高校までの文章の書き方とは異なるレポートの書き方、小論文の書き方など論理的な文章力をつけるための内容、「実践」は手紙の書き方など伝統的な日本語表現を学びながらエントリーシートの書き方に至るまで就職活動を視野に入れた実践的な内容、「応用」は歌の歌詞から日本文化を考察したり、エッセイやコラムなど自分の主張を説得力ある文章で表現する等の内容とした。
特に工夫をしてきたのは「基礎」の授業である。論理的な文章表現を中心に、接続表現や段落構成に注意しながら、文の修飾関係や読点の打ち方を効果的に用いる細やかな練習を行い、特に「事実と意見」の書き分けを重視し、グラフや表の統計データの分析を文章化する訓練に力を注いできた。
文学系の学科と比較すると、「書く」ことに苦手意識を持ち、読書体験が少ない学生もおり、語彙力を高めることも課題としてある。社会学系の学科であることを意識した内容を考える必要もあった。まずは新聞やテレビ等で社会情勢を知り、正しい情報に耳を傾けること、特に紙の新聞を読むことを推奨し、学科のリソースルームと呼んでいる、学生が自由に利用できる部屋では、学科の学びに必要な雑誌や新聞を並べている。しかし、世の中では紙の新聞を取る家庭が減っていることも事実であり、デジタル情報が席捲し、明らかに活字離れが進んでいる。このような状況においては、それらを止めるのではなく、むしろデジタル情報は活用すべきであり、正しい方法で有効に活用する手段をこそ探るべきである。
アナログとデジタルの共存に向けて
「基礎」の授業の具体例を挙げると、まず世の中の動きに関心を持ち、情報に敏感になり、そのことについて自身の考えを巡らす習慣を持つよう指導する。情報をただ受け入れ納得してしまうのではなく、疑問を持つことを強調している。そのための一方策として、1週間で気になった新聞記事を5件探して内容を要約するという課題を出す。当初は紙の新聞を読むことを推奨したものだが、近年は大学図書館が契約しているデータベース(朝日新聞クロスサーチ、ヨミダス、毎索、日経テレコン等)の活用を促している。データベース利用に慣れることに加え、適切なキーワード検索の必要性や重要性を学んでもらうためでもある。厖大な情報から自分が本当に必要とする情報を的確に手に入れることはそう容易なことではない。卒業論文のテーマを決めたり、参考文献を探したりするときに、必ずぶつかる壁でもある。
授業時には5件探した記事の中から1つを選び、1段落目に「事実の報告」(記事の要約)、2段落目になぜその記事に関心を持ったのか「理由」を、3段落目に記事の内容に対する自分の「意見」をまとめる、という作業をリアクションペーパーに縦書きで手書きしてもらう。これを3週連続して授業で取り組む。最初は書き終えるまでに40分~50分程度かかるが、慣れてくると30分もかからなくなる。
この練習は論理的文章を書く前のウオーミングアップに過ぎない。このあとに論理的な文章の「型」に当てはめて書く練習に入る。テーマは教員側で考え、4段落構成で書くという条件を出す。「事実の報告」(現状に関する客観的事実)、それに基づく「問題提起」を行い、自分の「意見」を提示し、意見に対する「根拠の説明」を行い、自分とは異なる意見を提示しながら反論を加えた自分の見解を主張、最終的な「結論」を出す、という構成である。学生が最も苦労するのは「問題提起」である。例えば「女性専用車両について、あなたの意見を述べなさい」といったテーマの場合、「女性専用車両は必要か必要でないか」など中立の立場に立った疑問の形を提示しなければ議論はうまく進まない。「事実」と「意見」の書き分けも重要になる。データベースで過去の新聞記事の検索機能を有効活用すれば、1912(明治45)年1月28日「東京朝日新聞」の記事に、女学生の体に触れたがる不良少年から女学生たちを守るために「婦人専用電車」を女学校の登校時と下校時に数回実施するという記事がヒットし、「女性専用車両」の先駆けとも考えられる「事実」を記載することができる。現在の女性専用車両が痴漢防止にどの程度の効果があるのか疑問を持てば、警察庁の「痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」等を根拠(事実)に引くなど、データを活用した「意見」を導くことに繋がる。小さな情報から視野を広げていく発想の転換も、論理的思考には重要な要素である。
日本語の能力は、英語やパソコンスキルと違って可視化する方法が少ない。当学科では授業に加えて、1年次から3年次までの各学年必須で年に一度ずつ「課題発見・解決能力テスト」(Z会ソリューションズ)を受験し、論理や意見の構築力等を試す機会を作っている。
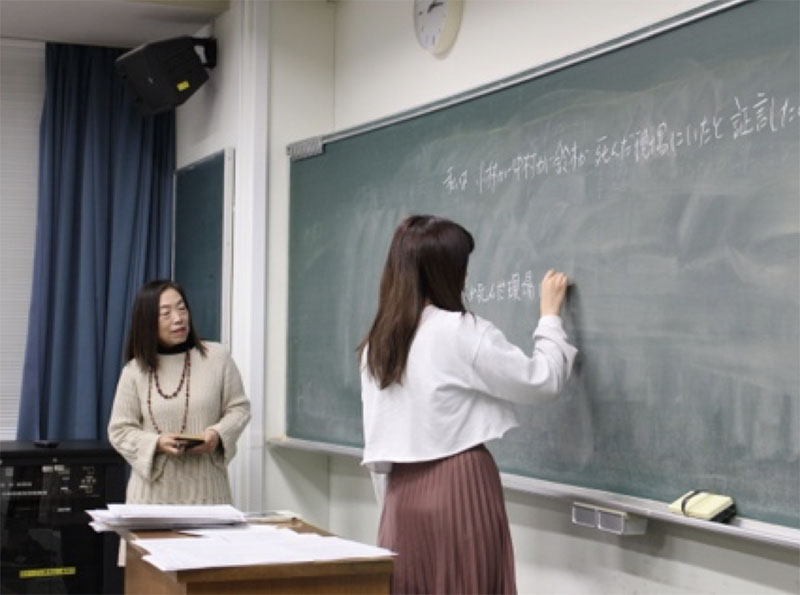

デジタル時代の「考える力」
デジタル化が進む現代において、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを叶える、便利で有効な技術を利用しない手はない。しかし、新しいものばかりに流されるのも抵抗がある。紙の匂いや手触りを確かめながら、手軽に行きつ戻りつして読み進める便利さのある書籍や雑誌。自分が求める情報や関心事以外のものが目に入り、つい余計な記事を読むことに時間を費やしがちだが多くの発見がある紙の新聞や辞書。それらを「無駄」と切り捨ててしまっては、大切な何かを失いかねない。
紙かデジタルか、という問題は「文化」のあり方にも深くかかわっている。演劇や演奏会に行く時間があったら、家でYouTubeを見た方が良いだろうか。映画館にわざわざ出かけなくても家でサブスクリプションの動画を見た方が良いだろうか。もしかしたら劇場に辿り着く途中で新たな景色に出会うかもしれないし、道端の花に癒やされるかもしれない。映画館の大スクリーンや場内の一体感で、作品の新たな魅力を発見するかもしれない。コスパやタイパが悪いと考える人の体を動かす対価(=魅力)が、多方面に求められているとも言える。
そもそも「文化」には無駄な行為が多い。目に見えない思考や思想、沸き起こる感情などを表現する行為、経済活動に直接結びつかない無駄と思われる行為こそが文化や芸術の根幹を支えてきた。意見を求められて様々なアイデアを出すと、採用されずに切り捨てられてしまうことも多い。かといって「考える」ことをやめてしまえば、良いアイデアは生まれない。ストレートに辿り着かず廻り道をすることも、時には必要なことがある。無駄が役に立つことも大いにある。コスパやタイパが重視され、デジタル化が進む現代だからこそ、無駄を無駄と思わない(思わせない)発想の転換、つまり「考える力」が必要とされている。
※中央教育審議会(文部科学省の諮問機関)はデジタル教科書を現在の教材という位置付けから正式な教科書とすることが適当とする中間まとめ案を大筋で了承した、との報道がある(山本知佳「デジタル教科書「正式化を」」 「朝日新聞」2025年2月15日 朝刊)。

福田 淳子(ふくだ じゅんこ)氏
昭和女子大学大学院 生活機構研究科・人間社会学部現代教養学科 教授
専門は日本近現代文学。川端康成を中心に、文学と映画・オペラ・演劇など他芸術との影響関係について研究。主な著書・論文は『川端文学におけるアダプテーション―「伊豆の踊子」の翻案を中心に』(ブックレット 近代文化研究叢書17、2024年3月、昭和女子大学出版会)、『川端康成をめぐるアダプテーションの展開――小説・映画・オペラ』(フィルムアート社、2018年3月)、『夏目漱石 修善寺の大患前後』(共著 近代文化研究所、2022年2月)、「火野葦平と向井潤吉―従軍がもたらしたもの」 ( 「学苑 近代文化研究所紀要」 2020年9月)など。


