田口 康大 氏
一般社団法人3710Lab(みなとラボ) 代表理事
Introduction
「海と人とを学びでつなぐ」をテーマに次世代の教育をデザインする3710Lab(みなとラボ)の代表理事田口康大氏。地球の70%を覆う海、生物の90%は海の中にいること。そして、気候変動と海の問題が密接に関わっているという事実をどれだけの人が知っているでしょうか。教育人間学の専門でもある氏から、「これからの海と人の関わり合い」についてお話を伺いました。
みなとラボは、「海と人とを学びでつなぐ」プラットフォーム。教育学者、科学者、エディター、デザイナーなど多様な専門家たちが、共に新しい学びを描き、深める取り組みを行っている。海と生きるとは何かという問いに向け、学校、地域、自治体に寄り添い、そして何よりも子どもたちと共に、さまざまなプログラムを実施している。
みなとラボから「海洋環境デザインプロジェクト」の内容を一冊にまとめた書籍を発刊しました。
海の楽しさをもっと広げたい
───田口さんとのご縁は、昨年2023年10月に行われた『OCEAN BLINDNESS─私たちは海を知らない─』のエキシビションでした。冒頭のメッセージを拝見した時、大きな衝撃を受けました。(以下抜粋)
私たちは海を知らない。
では、なぜ知らなければならないのでしょうか?
海は、地球の70%を覆っていて、生物の90%は海の中にいます。地球上で生物が生存できる安定した機構を作り出し、その豊かな資源と多様性で経済と文化活動を支えています。
海は、人に影響を与え、人から影響を受けています。
私たちの生命と暮らしを支えているのは、「海」そのものなのです。
今年の夏は、昨年よりもさらに暑く、異常気象を肌で感じる厳しい夏となりました。
私たちの穏やかな日々の暮らし。地球上でそのあたりまえを享受することが、そろそろ本気で難しくなってきています。
この先、私たちはどのようにして未来を選び取り、答えをだしていくのか。
海を知ることは、明日を知ること。自分自身を知ることです。
自らが選んだと言える未来のために、私たちは海を学ぶ必要があるのです。
───今回の取材で、目線を海に向けてさらに考えを深められれば幸いです。そもそも田口さんは、なぜ海に関心を持たれたのでしょうか。
田口 きっかけは2011年3月11日の東日本大震災です。当時、僕はドイツに留学中で、教育哲学や教育人間学を専門に研究をしていたのですが、自身も東北出身であり、家族や友人たちも多く沿岸部に住んでいたので、震災を目の当たりにした時「今すぐに研究をやめなければいけない」と感じるほどの衝撃を受けました。そこでひとまず研究のことは横に置き、被災地の子どもたちへの学習支援活動をはじめました。
そういった活動を継続していた2013年4月、ご縁あって東京大学の海洋教育センター(旧海洋教育促進研究センター)での研究活動の依頼をいただきました。海と教育のテーマは面白いなと思いつつも、正直私自身その時は具体的なイメージが湧いていませんでした。しかし、震災以来「これから先、海と人間がどう関わって生きていくのか」という問いをずっと持っていたので、お引き受けすることにしました。
しかし、学校教育現場の中で「子どもたちにどのように海を伝えるか」を考えたとき、学習指導要領という大きな壁がありました。学習指導要領に則ってつくられた国語、算数、理科、社会などの教科書の中では、海は断片的にしか取り上げられていないのです。まずは総合的に海を学ぶことのできるモデルを作らなければと考え、各地域の自治体や学校と連携し、独自に事業を進めていきました。
またその次に大きな壁を感じたのは、教育関係の事業をつくろうとすると「正しさ」が前提になってしまうことでした。「これは伝えなければいけない」「これにはこんな意味や意義がある」といった大人が考えた正しさで学びを縛りつけてしまうと、子どもたちがしんどくなってしまいます。そこで、大学教員の立場とは違う角度で「海の楽しさをもっと広げたい」という思いから、一般社団法人3710Lab(みなとラボ)を2016年に設立しました。
「対話を生み出す」みなとラボの活動
───「3710Lab(みなとラボ)」という名前の由来はどこから来ているのでしょうか。
田口 ネーミングには3つの意味合いがあります。まず1つ目は、陸と海の比率が3対7。3と7を足して全部で10になるという意味で「3710」です。2つ目は、それを「みなと(港)」と読ませるのは、港はいろいろな人たちが行き交い、集まる場所ですから、そういう場所になりたいという願いを込めました。最後に、海と関わるのは専門家だけでなく、誰しもに開かれているので、37で「み(ん)な」、10で「と」と読ませて「みんなと化学反応を起こそう」という思いが込められています。
───とても素敵な由来ですね!現在、みなとラボでは3つの柱①海の魅力を深める②人の考えを深める③学びのあり方を深める事業をされていますが、取り組みはどのように始めたのでしょうか。
田口 はじめは、渋谷の街を高校生たちと一緒に練り歩くプロジェクトでした。現在の渋谷と海の関係は遠いように感じるかもしれませんが、縄文時代、渋谷は海でした。「縄文海進」という現象で現在より海面が2~3m高かったのですが、歩いてよく観察すると、かつては海だったことが読み解けます。そういった自分たちにとって身近な場所や景色から、海とのつながりを学び、考えを深める試みを学校と連携して行いはじめました。
そしてみなとラボにとって大きな転機となったのは、2018年に行った宮城県気仙沼市の高校生とのプロジェクトです。気仙沼市の沖合に大島という島があるのですが、そこに橋を架けたいという40年来の構想がありました。今は橋が架かっているのですが、当時の高校生たちが「橋が架かることによって本土とつながり、島の文化が失われてしまうのは嫌だ」と反対の声をあげていたのです。もちろん、彼らは橋が架かることによる利便性も十分理解しているわけですが、子どもたちはただ純粋な思いで自分たちの大島の文化を残したいと願っていたのです。
僕は教育委員会から相談を受け、彼らの思いにどのように応えられるかを考えました。そこで、知人が運営している日本唯一の島マガジン『島へ。』という雑誌に、大島特集を高校生自ら作る企画ができないかと提案しました。コンテンツの企画、写真撮影、インタビュー、テキストを書いてそれをレイアウトするなど、プロの仕事同様の編集作業の全てを彼らが取り組み、その過程で自分たちが住む地域の文化や営みを知り、理解を深めます。そして、地域の大人たちとのコミュニケーションを生み出すことにもつなげたい思いがありました。
実際に雑誌編集をし、出来上がった後の報告会で改めて高校生たちが「自分たちはこれらの大島の文化を未来に残したいんです」と発表したところ、たくさんの大人たちが勢いよく彼らの元にわーっと集まってきたのです。本当に感動的でした。「対話を生み出す」という軸をすごく大事にして取り組んでいたので、その大切さを改めて実感した瞬間でした。


「その先」を考え、みんなで仕組みをつくる
───田口さんがお話しする声からも、みなさんの熱量がとても伝わってきました。そこからさらに他の地域や学校との連携に広がっていったのですね。近年では企業との協働もありますね。
田口 みなとラボで企業と共に取り組む際、2つの方向性があると考えています。1つ目は、すでに取り組んでいることを「届ける」。2つ目は、共同開発で「つくる」ことです。一緒に仕組みづくりを考え、ビジョンを作り込む協働のあり方が多いと思います。
例えば、海洋環境や海洋生物に深刻な影響を及ぼす海洋プラスチックは、その多くが「廃棄漁具」だと言われているのですが、三重県鳥羽市で廃棄プラスチックを再資源化している株式会社REMAREとの協働で、廃棄漁具を100%リサイクルしてつくった「umi frame」というフォトフレームがあります。これはデザイナー北川大輔さんにも協力いただき、4辺のパーツを紐で括ってシンプルに留めているつくりなのですが、この紐は漁網のほつれを修理する補修糸で、留め具は漁網をリサイクルしています。
大企業でも廃棄漁具をリサイクルして何かをつくることはできると思いますが、僕らはそのディレクションや意義づけをして消費者に届けていくところのアイデア出しを得意としています。そして、ただ購入いただくだけでなく、その先をつくっていかなければという想いを常に持って取り組んでいます。
───「その先」とは、具体的にどういったことでしょうか。
田口 消費者は、海洋プラスチックごみをリサイクルした商品を買ったら、社会貢献の一役を担えたとそこで満足してしまいますよね。実際はその先のほうが大事で、そこから海へ意識を向けてもらう仕組みづくりをしなければなりません。このフォトフレームを部屋に置けば、目に入った時に廃棄漁具のリサイクルのことや、自分と海との接点を何度も思い返す「装置」になると考えています。あまり重くなり過ぎずに、フォトフレームがある意義への思いを取り戻していける。美しいアートやデザインの力で、日常生活の中にいかに溶け込ませるかが大事だなと感じています。



───みなとラボにとって「デザイン」が大切なキーワードになっている印象を持ちました。田口さんはデザインをどのように捉えていらっしゃいますか。
田口 難しい質問ですね。いろいろな考え方があると思いますが、僕がデザイナーと取り組む時、例えばプロダクトそのものをデザインしてくださいというお願いではなく「その先までを一緒に考えましょう」と言うと、関わる全員がポジティブに楽しく取り組めるなと感じています。
プラスチックに関して言えば、デザイナーにとってはまるで夢のような素材だったわけです。思うように変形するので、自分の欲望を体現してくれる存在です。それが環境破壊に繋がっているとなると罪悪感を抱くこともあるかもしれませんが、プラスチックは私たちの生活を支えてもいるわけで、それを完全に否定するのも変な話ですから、一緒に仕組みづくりまで考えてデザインしていこうというのが僕らの合言葉になっています。
そして作る人だけでなく、使う人もプラスチックの恩恵に預かっているので、みんなで考えればいい。そして、作って終わり、買って終わりと安易に終わらせないことも大切ですね。対話には終わりがないものですから、問いをみんなで共有し続け、常に仕組み作りまで考える姿勢は大切にしたいです。
また、世界中の企業が今「海藻」に注目しています。海藻を増やせばそれがCO2を吸収し、ブルーカーボン※となるので、温暖化対策とビジネスの両輪で循環させる仕組みづくりが始まっていています。ヴィーガン人口が増えてきたこととも関係がありますが、食べ物という視点だけでなく海藻という“素材”を使って新しいプロダクトを開発する海藻テック、シーウィードテックという新しい言葉やビジネスも生まれていますね。海に目を向けてみると、海藻以外にこれまで見過ごしていた素材や技術が活かしきれていなかったとこに世界中が気づき始めています。まさにブルーオーシャンが広がっているのです。
※ブルーカーボンとは:2009年10月に国連環境計画(UNEP)の報告書において、藻場・浅場等の海洋生態系に取り込まれた(captured)炭素が「ブルーカーボン」と命名され、吸収源対策の新しい選択肢として提示。ブルーカーボンを隔離・貯留する海洋生態系として、海草藻場、海藻藻場、湿地・干潟、マングローブ林が挙げられ、これらは「ブルーカーボン生態系」と呼ばれる(国土交通省)


「共創」の「共」は、誰しもに開かれているということ
───海のことを知れば知るほど、未知なる世界と可能性に気付かされます。今号のテーマ「下目線」に対しては、率直にどのような印象を持たれましたか。
田口 実は僕の教育上のモットーは「ゆっくり急げ」に加えて、前に進まずに「いかに下に行くか」です。どうしても社会では、スピード感を持って前に進むことが前提になっているため、その場に立ち止まるのは怖く感じるかもしれませんが、焦らずに、ゆっくり足元を深く見渡してみると、実はそこにこそ自分たちがこれからの時代に生きていくための術や方法が見つかったりします。
また、海や環境問題に目を向けることも大切ですが、「実際に海に行ってみる」だけでいろんな思いが湧いてくると思います。そこで自分の中に芽生えた感情に気づくことが大事で、そこから“自分と海とのつながり”が自然と広がっていく。近年、人類学だけでなく「歩くこと」や「石」がブームになっているのを見ると、「自分たちが立っているところは、果たして一体何なのか」を確認したいタイミングなのではないかと感じます。
また別の視点となりますが、下目線の中には「教育」が含まれていると感じています。教育というのは、人間そして社会の土台で、目には見えない分厚い層をつくり、そして下支えする重要な役割を担っていると思います。マーケティング業界のみなさんが独自に持っている企業のリソースをどんな形で教育に溜め込んでいくか。そんな視点で考えてみると、教育現場に自分たちが何かを届けるだけでなく、一緒に何かやっていく「共創」が生まれるのではないかと思います。「共(Public)」は、誰しもに開かれていることであり、それは社会の土台としての教育につながっていきますし、決して競争になりません。みなとラボのリソースを生かしながら、海と人と学びの楽しさをご一緒に広げていけたら嬉しいです。
───本号の記事をきっかけに、新しい化学反応が起こることを願っています。本日は素晴らしいお話を本当にありがとうございました。
(Interviewer:蛭子 彩華 本誌編集委員)



田口 康大(たぐち こうだい)氏
一般社団法人3710Lab(みなとラボ) 代表理事
東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター特任講師。
青森県生まれ。秋田県を経て、宮城県仙台市で育つ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。2013年、東京大学大学院教育学研究科に特任講師として着任。教育学・教育人間学を専門とし、人間と教育との関係について学際的に研究している。現在は、学校の授業デザインや、学校を軸にした地域づくりに取り組み、新しい教育のあり方を探求している。座右の銘は、ゆっくり急げ(Festina lente)。


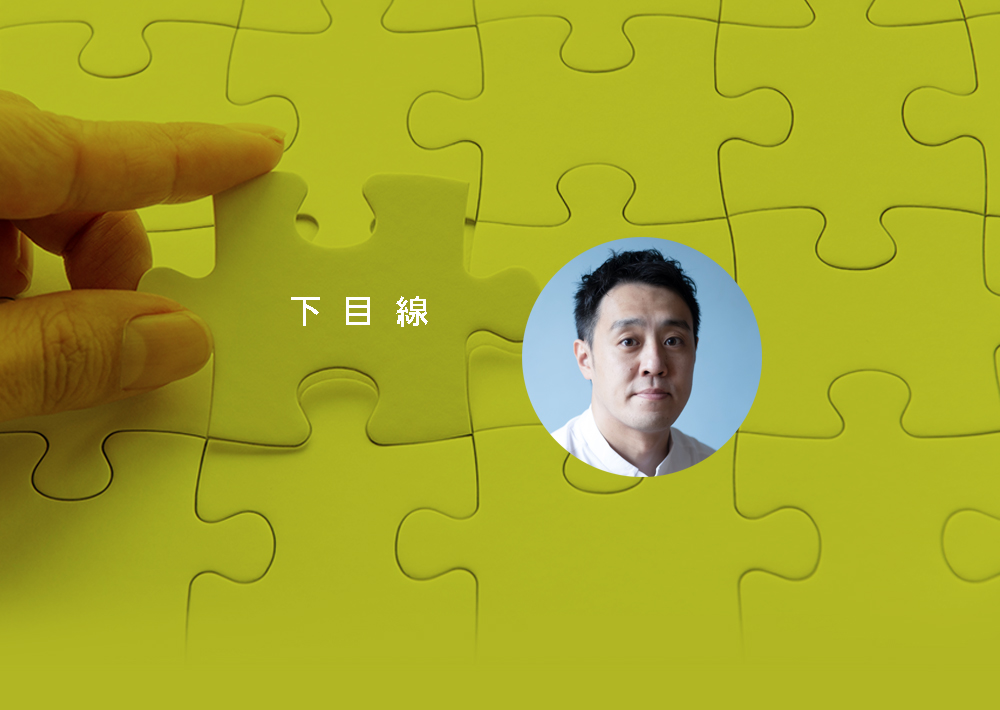
One thought on “私たちは海を知らなければならない~対話から“その先”を考える~”
Comments are closed.