メディアリテラシーと情報リテラシーの現状と未来
~投票行動と購買行動の比較相対化からの考察
見山 神保さんは、これまで一貫して情報リテラシーやメディアリテラシーの問題に取り組まれていますが、当初は想定されていなかったことが今起こっているのではないでしょうか。先ほどのメディアリテラシーの問題は、ジャーナリズムの崩壊という現状を見る限り、かなり認識されてきていると思います。その一方で、情報リテラシーという点ではますます複雑化しているように思います。メディアリテラシー、情報リテラシーについて、今、考えていることをお話しいただけますか。
神保 自分自身がネットメディアを主宰する立場から言うと、一つはとにかく信用できるメディアやジャーナリストを自分で見つけていくしかないと思います。自分が真に受けても大丈夫だと思えるようなメディアやジャーナリスト、もしジャーナリストという言葉が堅苦しければ、情報発信者でも構いませんが、いずれにしても信用できる情報源を自分で見つけていくしかない時代に入ってしまったのだと思います。
大手で有名なメディアであれば信用できるという時代ではありません。むしろ大手であればあるほど様々な利害関係の中にあり、政府との関係上でも既得権益を貪っている場合が多いので、最低限のメディアリテラシーがあれば、そんなメディアを信用できるはずがありません。
その一方で、幸か不幸かメディアは多様化しています。実際は玉石混淆で、残念ながらその中身は99%の石と1%の玉のような比率かもしれませんが、だとしても自分からプルできる(情報をひっぱる)選択肢ができたわけです。ただ、プルする選択肢ができたということは、逆に言うとプッシュもできるようになった。よく若い人たちに、プッシュされてくる情報はほぼ例外なくその後ろに何らかの利益、要するにお金が動いていることは知っておこうと話します。結局、いろいろなものが自分でプルできるような環境ができたということは、当然プッシュもできる環境ができたわけで、そのプッシュは、先ほどお話したアルゴリズムやポピュリズムとしての剥き出しのキャピタリズムなのです。それに太刀打ちする唯一の方法は、自分自身で信用できる情報源を見つけ、そこから自分で情報をプルするしかないのです。
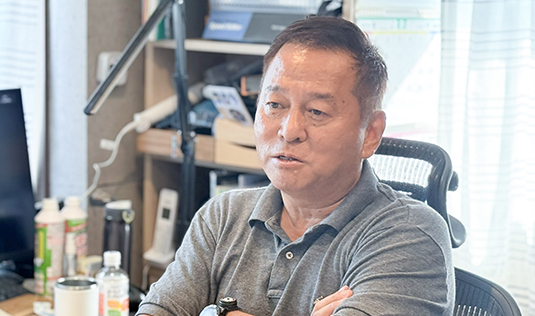
見山 結局、情報はあらゆるものに対して何らかのバイアスが掛かっています。取捨選択するのも自分の責任ですし、いろいろな情報を鵜呑みにしないで、どんな背景があるのか、別の視点はないかなど、自分なりに検証能力を高めていくことが重要ですね。そして、その情報を自分自身が選択したということに対して、メディアが言っていたから、SNSが言っていたからなど、他人任せにするのではなくて、自分がしっかり責任を持つということ、それしかないですね。
神保 そうしないと最後は自分が損をするよ、という話です。正しい情報を得られないと、自分にとって何の得にもならない勢力に清き1票を入れてしまうことで、結果的に自分が損をするわけです。自分ではもっとも良いと思うところに票を入れているつもりでも、良いという判断のベースになった情報に明らかなバイアスがあれば、その判断は誤っている可能性が高くなります。
見山 情報の波をかいくぐって、ファクトチェックをどこまで遡ってやるのかというのは難しいですよね。
神保 そもそもネット上で拡散されている情報には、根拠のないでたらめな情報が多いので、それを見分けるのは容易ではありません。全てが20秒単位の断片情報の海の中に生きている人が、今の日本や世界で起きていることをある程度の精度を持って理解することはかなり難しいと思います。
あまりにも断片的な情報が多く出回るようになったために、かつては一般常識として最低限これくらい知らないと世の中のことを正確に分からないと言われていたものが、あたかも専門的な情報であるかのように扱われるようになっています。
見山 確かに、専門的な情報と感じた瞬間に思考停止になる人は多いと思います。神保さんは、ポピュリズムの行き着く先をどのように捉えていますか。
神保 本来ポピュリズムには2つの意味があり、それは表裏一体の関係にあります。一つ目は「エリートや支配層に対して、庶民・大衆の立場に寄り添う政治」のことを意味します。しかし、もう一つ、「大衆迎合的で分断を生む政治」という意味もあり、これは同じものをどちら側から見るかによって見え方が変わるということです。
いつの時代も行き過ぎたポピュリズムは大きな弊害を伴ってきましたが、マスメディアの時代が終わりインターネットの時代に入り、まだ受け手側に十分なリテラシーが備わってない以上、少なくとも当分の間はポピュリズムが政治のデフォルトになることは避けられないように思います。
残念ながらそれが21世紀の民主主義の新しい形ということなのかもしれません。事実かどうか、正確かどうか、公共性はあるかどうか、中立性は担保されているかどうかといった、人類が長い年月をかけて培い育んできたジャーナリズムの基本原則をまったく無視した情報が、アルゴリズムによってプッシュされ社会で絶大な影響力を持つ。結果的に事実に基づかない多くの政治的な決定が下される。当然、社会は少しずつ悪くなるでしょう。問題は、社会が少しずつ劣化していった時、どこかのタイミングでそれに気づく人が現れ、いずれその流れを変えるようなうねりになるのか、それとも、ゆでガエルのように劣化に気が付かないまま、堕ちるところまで堕ちていくのかということです。
見山 なるほど。せめてできることがファクトチェックなのだとあらためて思いますが、「オルタナティブファクト」のような話が出てくると、それすらも難しいということですね。
神保 私はグーテンベルク革命の終焉という表現を好んで使っていますが、ことメディアに関する限り、人類はいまだかつて経験したことのない時代に突入していることが、必ずしも十分に認識されていないように思います。メディアにはコンテンツと伝送路の両輪があるのですが、14世紀にグーテンベルクが活版印刷を発明して以来、人類はコンテンツについては大きな進歩を実現しましたが、常にそれを人々に伝えるための「伝送路」の壁に直面してきました。インターネット以前は、伝送路が希少な存在だったために、ほんの一握りの特権的な立場にいる人たちが伝送路を支配下に置き、情報を発信する特権を独占してきました。しかし、あるときインターネット網の開放というビッグバンが起きて、これまで極めて希少だった伝送路が事実上無限化し、誰でも情報を発信できるようになりました。それは今までのマスメディアといわれるような少数の担い手によって情報の流れが支配されていた時代に比べれば、メディアの民主化の始まりではあったわけです。
このメディアの民主化というのは、政治の民主化ととても似たような比喩ができると思います。例えば、投票権を歴史的に見ると、過去には、ある年齢の一定以上の税金を納めている男性にしか選挙権がありませんでした。あるいは、その国における白人など多数派民族の男性で一定以上の税金を納めている人にしか選挙権はありませんでした。しかし突然、明日から全員に投票権を与えますということになると、それまで投票を前提に政治や社会を見ていなかった人たちは、自分たちの投票行動によって何がどう変わるかという感覚も持ち合わせていないため、かなりいい加減な理由で投票行動を決定する人も少なからず出てくるでしょう。一握りの特権階級が投票という特権を独占するのは決して良いことではありませんが、誰でも投票できることになると、最初はわけが分からない人たちが選ばれてしまうこともあるかもしれません。もちろんポピュリストが選ばれることも以前より多くなる可能性はあります。
長期的に見れば、普通選挙権が認められた方がより公正で公平な社会を作ることにつながるとしても、短期的にはポピュリズムが横行したり、十分な知識の無い人が議員に選ばれたりして、一時的に政治が混乱したり劣化したりする可能性は十分にあります。結局、その国の民主主義の質は、有権者のリテラシーに呼応せざるを得ません。メディアも同じような状況にあると考えていいと思います。
人類史でインターネットが開放され、伝送路が無限化したのは1996年から1997年のことで、まだ30年ほどしか経っていません。その一方でグーテンベルクが活版印刷を発明してから、伝送路が希少な状態は500年以上も続いていました。それが30年かそこらで、急にリテラシーが上がるはずがないのです。誤情報でも何でも使ってネット配信で小銭を稼ごうとするような人が大量に出るのも当然のことです。
見山 自分自身の承認欲求や広告収入のために発信する人たちですね。
神保 はい、非常に大きな仰々しい文字でサムネイルを作るノウハウだけは持っていて、選挙の際に話題性のある政治家の演説から刺さりそうな発言部分だけを切り出してYouTubeに貼り付けていくだけで1か月に50万円もの収入を得られたりするのですから。それはある日突然、投票権を得た人の中に、その権利を使って一儲けしようと考える人が出るかもしれないのと同じです。情報をアップする動機が、本当にその政策に賛同しているからではなく、受けそうなものをアップするだけでいいのですから。収入を得ることだけが目的であり、自分をジャーナリストだなんて微塵も思ってない人たちです。
見山 有権者の情報リテラシーを高めていく必要がありますね。
神保 今のままの状態が続くと、政治は混乱し続け、経済も停滞を続け、社会も劣化が止まらないため、結果的にそのツケを自分たち自身が払うことになります。
アメリカのトランプ政権を見ていて思いますが、あるとき突然、市場が「ノー」を突きつけてくる可能性があります。なので、最終的には市場とのチキンレースになるのではないかと思います。できれば市場に「ノー」を突きつけられる前に自力で修正できたほうが痛手はずっと軽くて済むと思いますが…。
見山 ここまでお話を伺って、情報の出し手の視点と受け手の視点というのは、別々に存在しているものではなくクロスしているということですね。
神保 今や出し手と受け手は完全に一体化していると思います。
見山 かつては、情報の受け手は弱い立場にあるといった考え方がありましたが、今はむしろ受け手自身が社会に対して影響力を持ち始めていることに自覚と責任を持つべきということですね。
神保 責任感とリテラシーというのも一つですが、そこで無責任な行動を取ることが、最終的にどういう結果をもたらすのかをいかにして可視化するかが重要だと思います。もともと、そのような強い倫理観は育っていないわけですが、誰も損はしたくないはずです。そういうことをやっていると回り回って最後は自分たちが損をするということが可視化できないと、その行動は改まりません。
見山 どうすれば可視化できますか。
神保 簡単ではありませんが、いろいろ手はあります。しかし、それを20秒で説明するのは難しいと思います。結局、信頼をベースにしたメディアと受け手の関係が構築できない限り、暇つぶしに付き合ってもらうことでアクセスを稼ぐ以上のメディアにはなり得ないということです。信頼関係ができていなければ、受け手がそこにとどまる理由は「笑える」「刺さる」「心が揺さぶられる」「感動する」などの喜怒哀楽を強烈に刺激してくれる要素が20秒以内に出てこなければなりません。そうでないと簡単に指先でフリップされてしまいます。結局、20秒で分かるような情報だけになると、全てがとても表層的なものになってしまいます。だからこそ表層的な情報だけが回り回って、どのように因果応報するのかということを可視化する努力をしなければならないと思います。
見山 大変興味深いお話をありがとうございました。
(Interviewer:見山 謙一郎 本誌編集委員)
投票行動と購買行動の比較相対化
~神保氏のインタビューからの考察
昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 教授 見山 謙一郎
政治については、特に若者世代の興味、関心が薄く、情報の受け手側に情報に対する免疫力やリテラシーがないことから、発信者がバズりそうな情報を発信し、実際の効果観察を繰り返すことで学習できる環境があると言えます。バズること自体が目的である情報の発信者は、バズりさえすればよいので、情報の精度や整合性、そして正確性すらも気にする必要はないわけです。そして、情報の受け手側に十分な情報リテラシーが備わっていなければ、情報は個人を直撃し、実際にバズります。つまり、共同体やジャーナリズムが崩壊した今、情報の受け手側のリテラシーが弱い政治のような情報は、現時点では情報の出し手側が主導権を握っており、投票行動に影響を及ぼすことが可能であると言えます。
その一方で、マーケティング領域においては、情報の出し手である企業よりも、情報の受け手である消費者の方が、インフルエンサーなど第三者が発信する客観的な情報の選択肢を豊富かつ多様に入手しています。インフルエンサーは玉石混淆ですが、消費者自身が購買行動に対する責任を自ら負っていることから、情報の取捨選択には慎重になるはずです。この点において、神保氏のインタビューの最後に語られている「表層的な情報だけが回り回って、どのように因果応報するのかということを可視化する」ことが、購買行動においては、ある程度できていると捉えることも可能です。また、信頼できるインフルエンサーからの情報は、かつての共同体やジャーナリズム的な視点からの情報提供と捉えれば、結果としてインフルエンサーは、消費者にとって、企業情報の直撃を受けない緩衝地帯としての機能を果たしているとも言えます。つまり、購買行動においては、情報の受け手側である消費者側に情報の選択権が委ねられており、学習環境が整備されていると言えます。この意味において、購買行動では、商品や製品、サービス等の情報の受け手である消費者側が主導権を握っており、情報リテラシーを有していると言えるでしょう。
このように、投票行動と購買行動を比較相対化することにより、情報の主導権が情報の出し手、受け手のどちらにあるかの違いはあるものの、両者の共通点は、情報の出し手、受け手いずれもが、技術の変化が激しい現代において、メディアリテラシーや情報リテラシーの学習プロセスの途上にあるということだと思います。
そして、今回の神保氏のインタビューから明らかになったことは、誰もコントロールしていないアルゴリズムに支配されるポピュリズムの世界とどのように対峙していくのかを、情報の出し手側も受け手側も強く意識し、学習していく必要があるということだと思います。「技術(アルゴリズムや生成AI) 対 人間」、「インターネット(SNS) 対 人間関係」、「ファクト 対 オルタナティブファクト」などの境界線が曖昧になっていく混沌とした世界では、自分自身で情報をプルできるようなメディアリテラシーと情報リテラシーを個々が高めて行く必要性をより強く感じました。そして、これらのことは、人間中心の価値観への回帰や、リアルな体験、一次情報がこれまで以上に価値を持つ時代であるということにあらためて気づくきっかけとなりました。
本特集号のテーマは、「学生(若者)と企業の認知距離~メディア、広告の現在地を踏まえた考察」ということで学生(若者)起点からの企画でした。しかし、情報技術の変化が激しい現代においては、世代や業態、そしてセクターの違いを問わず、メディアリテラシー、情報リテラシーを、失敗を含めた学習プロセスの中で学び、高めていく必要性を強く感じました。まさに「学生(若者)は、今の社会を映す鏡である」ということなのだと思います。そして、このことが本特集号で、大学教員として私が伝えたかったことなのかもしれません。

神保 哲生(じんぼう てつお)氏
ビデオニュース・ドットコム 代表
ビデオジャーナリスト
1961年 東京生まれ。1977年(15歳時)渡米。1980年 コロンビア大学入学。1981年 ICU(国際基督教大学)に転籍、1985年 ICU卒。1987年 コロンビア大学ジャーナリズム大学院修士課程修了。 米・クリスチャン・サイエンス・モニター紙記者(ボストン)、AP通信記者(ニューヨーク及び東京)記者、グローブ・アンド・メール紙(カナダ)東京特派員などを経て、1994年独立。1996年、日本ビデオニュース株式会社を設立、代表取締役に就任。1997年、衛星放送事業者免許(放送免許)を取得し、CS放送「スカイパーフェクTV」においてCNBCビジネスニュースの放送を開始。同年、CNBCの日本法人CNBCジャパンの取締役兼東京支局長に就任。1999年、CNBCと日経サテライトニュースの合併(現日経CNBC)を機にCNBCジャパンの持ち株を売却し、ニュース専門インターネット放送局「ビデオニュース・ドットコム」を設立。代表・編集主幹に就任、現在に至る。
2003~09年、立命館大学産業社会学部教授、05~12年、早稲田大学大学院ジャーナリズム学科客員教授などを兼務。
主要な取材テーマは地球環境、平和構築、メディア倫理、日米関係など。


