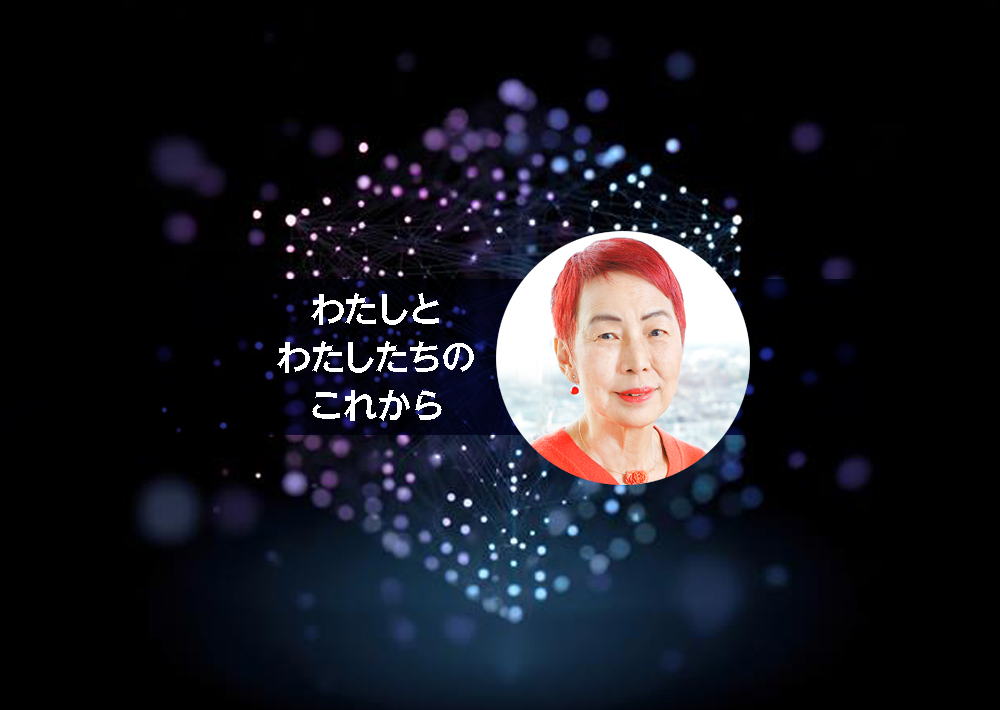上野 千鶴子 氏
社会学者・東京大学名誉教授、
認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長
*本記事は、『マーケティングホライズン』2022年第3号(4月1日発行)に掲載された内容を、Web版として再掲したものです。
156カ国中、120位。これは「ジェンダーギャップ指数2021」における日本の順位だ。ジェンダー格差だけでなく、少子高齢化、介護業界の人手不足など、日本が抱える課題を挙げれば枚挙に暇がない。他人行儀ではなく、自分ごととして生きていくためには。女性学で当事者研究のパイオニアでもある上野千鶴子氏に編集委員3名でお話を伺った。
蛭子 本号のテーマは「わたしとわたしたちのこれから」です。上野さんは、女性学で当事者研究のパイオニアとして“わたし”に向かっていかれ、研究で得られた多くの成果を私たちは学ばせていただいています。混沌とした社会の中 で“わたし”を見失うことなく、“わたしたち”のこれからをどのように描いていけるか。ご自身のご経験を伺いながら、本テーマについて考えを深められれば幸いです。はじめに、そもそもなぜ社会学を専攻されたのでしょうか。きっかけをお聞かせいただけますか。
他人ごとから自分ごとへ
上野 社会学を専攻したのは不純な動機で、消去法です。ただ一つの積極的な動機は、私が非常に好奇心の強い子どもだったということです。死んだものよりも目の前の生きて動いているものに関心がありました。しかし、社会学をやってみたらはっきり言ってつまらなかった。学問に価値がないとは言いません。大学に入ったら、男が男のために、男がいかに生きるかを考えて作られてきたことがわかるだけで、学問に女の居場所はありませんでした。
モラトリアムで大学院へ進んだ20代半ばに、アメリカに女性学があることを知りました。自分自身を研究の対象にしてもいいと、目から鱗が落ちました。そのとき初めて真面目にやる気が出ました。
社会学は類型化して外から見るという点でマーケティングと親和性が高いです。つまりは「他人ごと」です。しかし、私は女性学と出会ったことで、自分自身が研究対象となりました。当事者研究という言葉は当時ありませんでしたが、今から思えば女性学は当事者研究のパイオニアでした。
けれど、大変な目にも遭いましたよ。学問は中立的で客観的なものであり、女が女のことをやると主観的で、それは学問ではないと散々言われました。今でも女性学は二流の学問だと思われています。頭の悪い女のやるものだとか。優れた業績を上げた女性がジェンダー研究に行くと、惜しいことをしたと言われたそうです。
局所化されてきた多くの課題
松風 今のお話からフラストレーションに近いエネルギーの強さを感じました。それが自分に向かっていく時、上野さんはご自身の無限大の可能性を感じられたのでしょうか。
上野 自分が女であることは巨大な謎でしたから、解くべき問いが山のようにありました。自分が女であることと折り合いがつかない。多くの女の子たちはそういう経験を10代からすると思います。女という謎に立ち向かってみると解かれていない問いがいっぱい。アンネナプキンの登場前には月経用品は何を使っていたのか、お産の場に男は立ち合ったのか、授乳のしかたはどう変わったのか、なぜ女の子は自尊感情が低いのか・・・自分の可能性というよりも、女性学には無限大の可能性がありました。
私たちは女性学をジェンダー研究に変えてきましたが、ジェンダーとは男女の非対称な関係性のことです。当たり前ですが、一方が変われば、他方も変わらざるを得ません。女が変わったのに、男はこの数十年間、ほとんど変わっていません。すべて女の問題であると局所化されてきたのです。
1985年の男女雇用機会均等法成立以降、社会が変動するのに十分な一世代分の時間が経ちました。世界的な動向を見ていると、その間に改革をやってきた国と、そうでない国の違いがはっきり出ており、日本は変わらなかった方の国です。しかし、一見女だけに選択肢が増えたように見えます。男は仕事だけ、女は働いても働かなくてもいい、働くにしてもフルタイムでもパートでもよい。とはいえ、それは自由な選択と言えるでしょうか。女性は家庭責任に加えて家計補助型の仕事を負わされています。つまり、家事育児にしわ寄せがいかない程度の仕事を夫に許可されてやるということです。今働いている女の10人に6人は非正規で、しかも、それは今や家計維持のために必須になっています。これが日本のマジョリティを占め、私たちはこれを新・性別役割分担と呼んでいます。
企業では一般職か総合職かのコース別人事管理制度を導入し、女性総合職は倍率が高く一握り。一般職で採用しても何年か見ていると、その人の伸びしろがわかるものです。コース転換という制度を導入したところもあるけれど、転換のハードルがまたやたらと高い。そのため、最初から同じカテゴリーで採用し、働きぶりを見ながら配置転換していったほうが、人事の上ではむしろ効率的だったと後で反省する人事担当者もいました。
基本的に女は補助労働力という仕組みの結果、何が犠牲にされたかというと、女の意欲と能力が犠牲になりました。企業にとって貢献するだけの力量を女はもっているはずなのに、女の意欲をくじくことで、日本の企業は非常に大きな外部不経済を生んできたと思います。企業にとって人材の能力と意欲、どちらが大事かといえば、もちろん意欲です。労働者の能力にたいした差はありません。能力を発揮してもらうための意欲をどう引き出すかを考えることが人事や経営者の役割でしょう。
小さな達成感が大きな意欲を育む
蛭子 ご自身が教育者になられたとき、学生の意欲をどう引き出していったのでしょうか。
上野 私は「でもしか教師」で、はじめは渋々の思いで就いた職業でした。長い間、経営基盤の弱い私学で教師をしましたが、新設の大学だと、完成年度まで私学助成金はびた一文も出ません。教師の給料の原資は学生の授業料です。ある時私は、学生が卒業するまでに支払う学費と、卒業に必要な単位数とで1講義あたりいくらになるかを試算しました。すると、1講義5,000円。仮に一括払いではなくばら売りで、教室の入口で5,000円ずつ払って出席すると考えたら、学生は来てくれるでしょうか。
そこで、職業倫理としてこの子たちに払った分の元は取らせてあげなければいけない。そして、ありものの知識ではなく、ちゃんと生きていけるような知恵をつけてあげなければならないと考えました。知恵というのは、問いを立て、それに答えを出す力です。見たことのない問いにぶつかったとき、どうやって問いを立て、どうやってそれを解くかというノウハウを教えることはできると思ったので、私は弱小私大で教育に燃えました。
多くの子どもたちは、やればできるという達成感や成功体験がなく、マイナスから出発しています。彼らの口癖は「どうせ」「しょせん」です。まずそれをゼロに引き上げるために一苦労しました。その次に、ゼロのスタートラインから成功体験を持ってもらうための1つの条件は、できるだけハードルを低くすること。教育者ができることはそういう仕掛けを作ることだと思います。基本的に東大での教育は、偏差値4流大学(というと差別用語ですが使わせてください。なぜなら本人たちがそう言ったので)で実践した教育法と同じことをやりました。子どもはどの子どもも同じだということがよくわかったからです。
今でも忘れられない言葉があります。私学時代のある学生が卒業前に私の研究室にやってきて「先生、ボク、頭は持っていたけど、使い方知らんかっただけやった」と言って出て行きました。それに感動したのは「ボク、アホやった」とは言わなかったことです。頭を持っていたけど、使い方を知らなかっただけというのは、自分自身に対して誇りのある言葉です。
教師になる前、様々なところで女性学の研究会を行ってきました。そこで、一人ひとりの女の人を舞台の上に引っ張り出して主役にし、彼女たちの経験を言語化して理論化する仕組みを作りました。例えば、助産師さんの仕事の話、障害児を産んで涙をのんで仕事を辞めた教師の話、あるいは主婦の話を淡々としてもらうのです。教育は、学校教育だけではなく社会教育も含みます。女性学は大学の外の勉強会や公民館で育ちましたから。自分と立場の違う女性たちと沢山接した経験が、学校教育にもつながっています。
怒りの感情に正しく向き合う
ツノダ 特に女性は、涙の裏にある本来感じている怒りをきちんと表現できる環境がない。それを表現したところで、周囲が叩く風潮があるのではと感じます。
上野 女性学の研究者であるキャロリン・ハイルブランが「怒りとは女性に対して最も禁じられた感情である」と言いました。とても腑に落ちました。女は怒ってはいけないのです。女が持っていい感情は、妬み、そねみ、恨み。これは、絶対に打ち勝つことのできない強者に対して弱者の持つ感情です。怒りは対等な人間同士の間で、自分の権利が侵されたときに感じる正当な感情で、自分のプライドを守るためのものですから。最近のアンガーマネジメントを見ていると、怒りをコントロールするよりも、正しく怒る方法を学ぶ方がよっぽどいいのではと感じます。
松風 上野さんは今、幸せですか。
上野 幸せの定義ができないので難しい質問ですね。ただ、私はおかげさまで機嫌よく暮らしています。
ツノダ 機嫌よく暮らすために、上野さんにとって一番必要なものは何でしょうか。
上野 イヤな人と付き合わないことですね。ストレスは他人から来るものですから。
ツノダ 大事ですね。大事なのにできる人が少ないかもしれない。女性だけでなく男性も含め、不満や怒りを抱えるこの日本社会で、上野さんが感じている希望があれば教えていただけますか。
上野 ため息が出てしまいますが、もしかしたらもう日本に希望はなく、本当に泥船で沈んでいくだけかもしれません。外国からゲストが来日して、彼らがよく言うのは「官公庁、自治体、企業のトップに会ったが女は1人もいなかった。日本の女はどうなっているのだ」と。それに対して「あなたは行く場所を間違えている。そんなところではなく、日本には無位無冠の強力な女たちが草の根にたくさんいる」と答えます。
草の根活動の女たちと長らく付き合ってきたことが、今の私を支えています。私は、主婦たちを侮ったことはただの一度もありません。もしこの人たちがしかるべき地位に就いていれば、夫より出世していたのではないかと思うほど有能な人が沢山います。
結局、日本社会はこの人たちに受け皿を用意しなかった。しかし、意欲のある人たちは自分たちで活動の場をつくってきました。私は現在NPOを運営していますが、NPOや地域活動を行ってきた女たちの底力を本当に信頼しています。
例えば、日本の介護保険。高齢者介護の研究に取り組んでいますが、日本の介護保険の制度は世界に対して誇るべき内容を持っています。ただし、マンパワーと予算の規模からいうと、福祉先進国とは比べものにならないくらい貧困で、それを批判する人が山のようにいますが、私は擁護する側です。
ある人から「上野さんが介護保険を信頼できるのは、それを担っている人たちを信頼できるからだね」と言われました。制度に欠陥はたくさんありますが、介護を担っている人材とケアの質は世界的に見て決して引けを取りません。それだけの底力を日本の市民は持っていますし、その中に無位無冠の女たちが沢山います。
ツノダ その人たちの存在が希望の1つでしょうか。
上野 そうですね。彼女たちが少しずつ制度を変えてきましたから。介護保険を作らせたのも非常に大きな達成です。私たちの世代の女には社会に受け皿がありませんでしたが、次の世代は、お金につながる仕事を自分たちでつくり出し始めました。その背景にあるのは、女に経済力と購買力ができたことと不可分です。女に財布がなかったら、マーケティングもへったくれもないですよね。
人間というままならない生き物に向き合う
松風 介護のお話の延長で、老いについてお伺いしたいです。親の老いる姿を見ながら、自分も将来、依存的な存在になっていくことに対して葛藤があります。上野さんご自身は、老いとどう向きあわれているのでしょうか。
上野 介護研究をして良かったのは、自分よりも先に老いて死に近い人の道筋を観察できたことです。今の社会で私たちが簡単に死ねない理由は何かといえば、栄養水準、衛生水準、医療水準、介護水準を上げてきたからです。水準を下げれば、あっという間に死にます。発展途上国に行けば、感染症が原因で40代くらいで死んでしまいます。
ツノダ 老いて自分の思う通りに生きられない葛藤を考えると、怖く感じてしまいます。
上野 そもそも、私たちは自分で自分の思うように体を動かせるでしょうか?高いところにある物を取る時に、1メートル以上ジャンプできる人がいるでしょうか。人間は、自分のカラダさえ思い通りにできない、ままならない生き物です。
もしあなたが病気になったり、障害を持っていたらどうしますか。子どもはもっとままならない他人です。人生とは、そういうものと付き合って生きていくということだと思います。病人になっても、障害を持っても、死なずにすむ。子どもが障害を持って生まれてきても殺さずにすむ。あれもこれも、望んで作りだしてきた文明の成果です。親の老いる姿を見て葛藤するのは、あれほど強かった人が弱くなっていく姿を見るからですね。それは、最高の教育だと思います。
一番依存的な存在は、新生児と死にゆく年寄りですが、それをこれまで100%の家族の責任にして、家族の中だけに閉じ込めてきたのです。女はそのケア役割をワンオペでやってきたのです。ようやく育児や介護は「家族の中で、女がたった1人でやることではない」というコンセンサスができてきた。そうでないと、もう女の人たちが潰れてしまう。実際に潰れて悲鳴を上げている人もいます。その負担を社会全体で分担するために、制度を作ってきたのです。例えば、育児支援や介護保険です。介護保険がなかった時代へは戻れません。
松風 怖いと思ってしまいましたが、介護保険ができる前と比較すると、安心できる時代になったのですね。
上野 他人に頼んだ場合には、きちんと対価が発生する。昔は対価がなかったのですから。私は、嫁の介護を、感謝なき介護、対価なき介護、評価なき介護と呼んできました。
介護保険法は2000年に施行されましたが、この約20年間で巨大なマーケットを作りました。介護保険サービス市場で育った事業者や働き手たちは、日本の財産だと思っています。私のようなおひとりさまで子どもがいなくても、安心して暮らせる社会です。子どもがいなければ、一昔前には「みじめ」の一言でしたから。
生身の人間がマーケットをつくる
蛭子 不安という感情から、マーケットが誕生し、人材が育つというプラスな面もあるのだと感じました。
上野 現場で育つ経験知を専門用語で、ローカルナレッジ、クリニカルナレッジと言います。学者や役人が机上で考えついたものではなく、生活体験の中から生まれた経験知です。情報の発生する現場は、そういったローカルな場です。
例えば、ある非常に質のよい介護実践を行っているデイサービスの女性経営者に会った時、その人が「血はつながっていないけれど、私たちは家族です。家族のようなケアをめざしています」と言いました。私は食い下がり「家族のようなとは、どういう意味ですか?でも、皆さんは、家族にできないことをやっておられるんじゃないですか?」と聞きました。すると、その女性がふっと「あ、そうね、私たちは家族にできないことをやっているわね」と言ったのです。さらに食い下がり「今、家族にできないこととおっしゃいましたね。それは何ですか?」と。その次に出てくる台詞をもし当てたら、皆さん方は偉いです(笑)。
ツノダ 家族にできないこと・・・・。
上野 これは、介護経験がないと言えないかも。彼女の口から出てきたのは「優しくなれること」でした。これがわかった人は苦労人です。この一言の背景に、どれだけの思いがあるか。どれだけ家族介護の現場をその人が知っているか。どれだけ家族介護が追い詰められているか。その後、私は「あなたたちは、家族にできないことをやっていらっしゃいます。であれば、“家族のような”と言うのをやめましょうよ」とお話しました。
ツノダ まさに机上の研究からは絶対に出てこない言葉ですね。どんなにAIが発達し、どんなにビッグデータを扱って分析しても、その一言は絶対そこからは出てこない。自分で見聞きした、現場の情報を大事にしたいと感じました。そして、その一言を聞いたときに、それが大事だと思える感性、目線を持っていることがすごく大切だと思いました。
上野 全くおっしゃるとおりです。AIが持っているのは、ありものの知識です。ありものというのは、自分以外の誰かが生産した知識で、他人がつくった情報は全てセコハン情報です。セコハンとはセカンドハンドのことで、人の手を一度通ってきた二番手。学生に論文を課す時は「セコハン情報は絶対許さない。一次情報を取ってこい。自分がゲットした現場の情報を分析の対象にしなさい」と伝えてきました。
ツノダ 分析者が生ものに向き合う目。生きの良さを見極める目を養うにはどうしたらいいのでしょうか。
上野 それは簡単です。子どもは好奇心の塊なので、それを潰さなければいいのです。それまで子どもたちは、何か言ったときに無視された、押さえつけられた、そんなバカなことを考えるんじゃないなどのネガティブなことを言われ、自分の意欲を低下させられてきています。そのときに「おもしろいことを考えついたね、私もよくわからないから一緒に考えてみようか」と大人が言ってくれれば変わります。
ツノダ 新入社員に対しても同じでしょうか。
上野 何歳になっても同じです。成人を相手にした社会教育の講師も務めましたが、60~70歳を過ぎた人でも、タケノコが皮を剥ぐように育ちます。その人が自分で成長したいという意欲を持っていたら、本当にぐんぐん変わっていく。しかし、そういった経験をこれまで味わったことがないのだろうなと思う人によく会います。同調性は、日本の国民性でも何でもありません。
ツノダ お互いに異なる意見を言い合える土壌や、言い合う習慣があまりにも日常的にないまま大人になった人が多いのではと感じます。
上野 私のゼミでは、発表者に対して質問が出たとき、返答後に質問者に必ず「Did he or she answer your question?」(今の答え、あなたの質問に答えたことになった?)と、確認します。そう聞くと、「いや、私が聞きたいのはそこじゃなくて」とか「ここはいいけど、ここの部分が納得できない」とかフィードバックが返ってきます。他人の言うことに100%同意することはありません。一部は同意するが、他の部分には同意できない。そうやって議論を詰めていくところから、次の一歩が生まれます。日本のゼミでは、質疑応答が一問一答で終わってしまいがちです。すれ違ったまま、飲み込んで黙る習慣があるようです。きちんとかみ合う会話になっておらず、互いの意見が、双方に影響し合う経験があまりないようです。最悪の例が国会の論戦ですね。マーケティングの業界がそうであったら、最低じゃないですか。
蛭子 それは会社も同じだと思います。空気を乱すような発言をすれば、自分がおかしいのかなと萎縮してしまって、その後も何も言えなくなってしまうことがあるのではと感じます。
上野 「人と違うことを言ってもかまわない」という、その場の空気があるかどうかが大切ですね。卒業生たちが書いた『情報生産者になってみた』(ちくま新書、2021年)の本の中で一番嬉しかったのは「あんなに権威主義的でない空間は味わったことがなかった」と言ってくれたことです。何を言ってもかまわない。何を言っても賞罰を受けない。そういう場が、学校や職場に少ないのでしょう。
ツノダ 心理的安全性という言葉を最近よく耳にしますが、安心して話せる環境を家庭、そして組織内でつくっていくことが大切ですね。そして自分自身、ノイズや直感、自分の内なる違和感を大事にして、流されずにきちんと伝えられるような姿勢をもって生き続けたいと改めて思いました。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。
《インタビューを終えて》
■ 蛭子 彩華
上野さんにご紹介いただいた学生や女性の言葉には、血の通った人のあたたかさがあった。それらの言葉を引き出すために、時に“食い下がり”離さない。時間を惜しまず、諦めず、納得するまで対話をする。それは、「自分の気持ちを言葉にすること」そして「安心して言葉にできる環境をつくること」で達成される。それこそが“わたしとわたしたちのこれから”を前向きに、そして生き生きとしたものにするために必要なことであり、そのためにも、まずは自分自身が言葉にすることを恐れず、そして目の前の人の言葉を聞き逃さずに生きたいと感じた。改めて「誰しもが喜びも怒りも持ち合わせた“生身の人間”なのだ」と肝に銘じる機会を頂いたことに、心から感謝申し上げたい。
■ 松風 里栄子
自分の感情に正直に向き合うこと。これが大人になればなるほど困難になる。“優しくあれ、強くあれ、怒りを抑えなさい、泣くのは大人ではない、、、” 社会性というヘルメットをかぶり、自分自身を解き放つことを我々は時に忘れる。そこには自分の感情を吐き出せば、傷つくかもしれないというディフェンスメカニズムも働いている。上野さんは、そんなヘルメットやメカニズムを取り払った時に人は自分の真の可能性に気づく、ということをまさにご自身と、上野さんが関わる学生やコミュニティで示しておられる。勇気とパワーをいただいた取材となったが、その源は上野さんの厳しくも暖かい人間性と、人に対する飽くなき好奇心だと感じている。
■ ツノダ フミコ
世間一般、あるいは多くの男性が上野さんを語る際の頻出ワードに「こわい」があるが、ひと頃話題になった東大入学式の祝辞や数々の著書には優しさと寛容が滲み出ている。どの立場から上野さんの言葉を受けとめるかにより印象が大きく変わるのだろう。このたびのインタビューにおいてもそれを実感した。静かで澄んだ声に凄味を感じるのは、現場の実態と声を集め、N=1に潜む社会課題の解決に向けて動いていくのだという強い意志の所以だ。オンラインのインタビューではあったがにこやかに鋭く返すその迫力に何度もたじたじと後ずさりしつつも、懐の深さと柔らかさでそのたびに引き戻される、そんな心地良い時間をいただいた。これだ、これが上野千鶴子なのだ。
(Interviewer: 蛭子 彩華、松風 里栄子、ツノダ フミコ いずれも本誌編集委員)

上野 千鶴子(うえの・ちづこ)氏
社会学者・東京大学名誉教授
認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長
富山県生まれ。京都大学大学院社会学博士課程修了。平安女学院短期大学助教授、シカゴ大学人類学部客員研究員、京都精華大学助教授、国際日本文化研究センター客員助教授、ボン大学客員教授、コロンビア大学客員教授、メキシコ大学院大学客員教授等を経る。
1993年東京大学文学部助教授(社会学)、1995年から2011年3月まで、東京大学大学院人文社会系研究科教授。2012年度から2016年度まで、立命館大学特別招聘教授。
2011年4月から認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長。
専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理論家のひとり。
高齢者の介護とケアも研究テーマとしている。